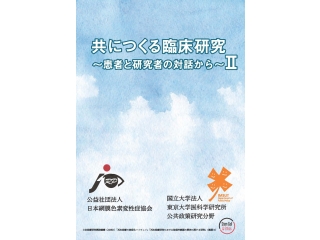※このイベントは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催方法を変更いたしました。以下の通り、ウェビナー(インターネット中継によるセミナー)として開催させていただきます。
医療現場でのAIの利活用は、どのような点に留意して進められるべきでしょうか――この問いを一緒に考えてくださる方を募集します。
「AI」「人工知能」という言葉に接する機会が随分増えてきました。新聞やテレビ番組、商品を紹介する広告などで、関連する情報が毎日のように登場しています。医療においても、AIの活用によって、私たちの通院や診療が一層便利に、またより充実したなものになることが期待されています。一方、こうした展開によって、我々が新たな悩みや課題について直面することもあるかもしれません。そこで、「みんなで考える医療AI」検討会を開催することになりました。
当日は、医療AIの現状と課題を知っていただくとともに、架空の事例をもとにしながら、患者・市民の視点からみた課題と解決策を探していきます。この検討会に参加し、感想や意見を提供くださる方を募集します。皆さんのご応募を心よりお待ちしております。
| 日程: | 2020年2月22日(土) |
|---|---|
| 時間: | 14時から15時20分頃(予定) |
| 対象: | 医療AIの利用に関心をおもちの患者・市民の皆様(医療関係者、製薬企業関係者、AI開発企業関係者の方はご遠慮ください) |
| 参加費: | 無料 |
| 申込方法: | 事前のご登録が必要です。次の【参加者へのご案内】をお読みの上、ボタンをクリックしてお申込下さい。 |
| 主催: | 厚生労働科学研究費補助金「医療におけるAI関連技術の利活用に伴う倫理的・法的・社会的課題の研究」(研究代表者:井上悠輔) |
| 共催: | 認定NPO法人 ささえあい医療人権センターCOML、文部科学省新学術領域研究「システム癌新次元」「ゲノム解析の革新に対応した患者中心主義 ELSI の構築」(研究代表者:武藤香織) |
内容:
- 開会
- 医療AIとは何か?
研究代表者より、医療AIに関するこれまでの議論や課題を紹介します。
Zoomの機能を使ったご質問やご意見をお寄せください。資料は前日に配信いたします。
<ご参考:テレビ会議ソフト Zoomの基本基礎> - 仮想事例の検討:スマートフォンのアプリを使って「ほくろ」を見分ける
皆さんに事例を通して様々な論点を考えて頂きます。Zoomの機能を使ったご質問やご意見をお寄せください。
資料は前日に配信いたします。 - アンケート記入
以下のウェブアンケートのサイトからご記入いただきます。
https://questant.jp/q/MedicalAI_ELSI (当日に接続可能となります) - 閉会
当日の参加方法:
Zoomというウェブ会議システムを使用します。パソコンやスマートフォン、タブレットからアクセスしてください。ご家族やお友達と一緒にお聞きくださっても構いません。アクセス方法は、お申込み後、前日にご連絡いたします。
参加者へのご案内
(1)利用方法とテスト接続について
Zoomを初めて利用される方は、パソコンの場合には、https://zoom.us/にアクセスしてご準備下さい。
スマートフォン、タブレットからアクセスする場合は、Zoomで検索してアプリをダウンロードして下さい。
事前に操作方法を確認してください。接続に関するサポートはできませんので、ご了承下さい。
<テスト接続(ご希望の方のみ)>当日13時から14時頃
前日のご案内する、「当日の参加用URL」にアクセスすると、テスト接続ができます。
(2)進行中に頂くご質問やご意見について
Zoomの機能を使って、ご質問やご意見をお寄せ下さい。お寄せ頂いた内容は、進行中にご紹介することがあります。
頂いたご質問やご意見の全てにお答えすることは難しい場合があることをご了承ください。
公共の場での投稿として不適切な投稿と主催者が判断した場合には、削除、凍結させて頂く場合がございます。
具体的な投稿方法は、前日にご連絡いたします。
(3)記録について
当日は、Zoomの録音、チャットの内容の記録をさせて頂きます。
文字起こしされた録音データやチャットの記録は、共催者である認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOMLの会報の記事や
研究班の報告書に使用することがあります。録音データやチャットの記録は公開いたしません。
本日第9回公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:2月12日10時~12時半頃
| 発表者1: | 李 怡然(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任研究員) |
|---|---|
| タイトル: | 遺伝性腫瘍に関する家族内での情報共有の課題点 |
要旨:
報告者はこれまで、家族内における遺伝情報に関する「リスク告知」というテーマについて、遺伝性腫瘍を事例に取り組んできた。遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)は、予防・治療法といった対処可能性(actionability)の高い代表的な遺伝性腫瘍であり、疾患の早期発見や予防のために、積極的に血縁者と情報を共有することが、医療専門職の学会ガイドライン・指針等で推奨されている。これまでの遺伝性疾患に関する先行研究では、親から子に伝える葛藤や困難に着目することが多かったものの、患者からきょうだいや親世代を含む親族、友人や職場など家族外へ打ち明ける際の課題点は、十分明らかにされていない。本報告では、HBOC患者が、家族らと情報共有を行うことにどのような態度を有しており、相手からの反応によって生じるジレンマにどう向き合っているのか、インタビュー調査の結果を紹介し、情報共有における課題点を検討したい。
| 発表者2: | 井上 悠輔(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 准教授) |
|---|---|
| タイトル: | 非倫理的な研究論文の原稿の取扱いについて |
要旨:
2018年の中国での胚ゲノム編集に関する報告は様々な波紋を呼んできた。本発表では、先月号のネイチャー・バイオテクノロジー誌のエディトリアルを素材としつつ、特に発表倫理との関係から検討したい。この試行については、学術的に十分に評価されていないこともあって、様々な憶測を呼んでいる。最近、この研究者らが投稿していた原稿の一部が第三者に流出したことが確認され、新たな論点となっている。プロセスに課題の多かった研究で得られた知識をどのように取り扱うべきか。研究倫理における過去の議論と2015年の拙稿を振り返りつつ、今回の出来事を整理して、その位置づけを図りたい。
D1の飯田です。
このたび、「生命保険経営」に以下の論文が掲載されました。
飯田寛、武藤香織
英国の「遺伝学と保険に関するモラトリアム協定」
生命保険経営第88巻第1号、26-41(2020.1)
発症前遺伝学的検査によって将来の発症が予測される人々が生命保険に加入できないもしくは高額の保険料を払うことは差別だとして海外では保険会社での発症前遺伝学的検査の利用を制限しています。一方で日本では今のところこのような規制がありません。
そこで、本稿においては、今後の日本の生命保険での発症前遺伝学的検査の利用に関するの議論の参考にするために、英国の政府と保険業界の取決めという形態での発症前遺伝学的検査結果の利用を制限した議論の経緯について文献調査および英国保険協会へのインタビュー調査をおこないました。英国を対象にした理由は医療制度が国営であり、日本の皆保険制度と似ていることから、生命保険の死亡保障を対象に議論がなされているからです。英国での早い議論の展開や、政府と業界の取決めという形態とした背景、発症前遺伝学的検査の適用を判断する仕組みなどの要点を整理し考察をおこないました。
英国と日本での環境や考え方の違いは考慮しなければなりませんが、今後の日本での議論の活性化の一助になればと考えています。
ご関心のある方はご一報ください。
東京大学医科学研究所 学友会セミナーのお知らせ
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/events/gakuyukai/archive/post_873.php
| 開催日時: | 2020年1月24日(金)10:00~11:30 |
|---|---|
| 開催場所: | ヒトゲノム解析センター3F セミナー室 |
| 講師: | Jon F Merz |
| 所属・職名: | Associate Professor of Department of Medical Ethics & Health Policy, University of Pennsylvania |
| 演題: | Waivers of Informed Consent for Research: A Legal and Historical Review and Consideration of Emerging Practices |
概要:
Waivers of informed consent for research are broadly permitted by national regulations and international ethical codes, and there is movement to expand the use of waivers in clinical trials. In this talk, I summarize several threads of current research that explore the legal and policy background to the development of waivers in United States policy and regulation. I also describe several completed and on-going systematic reviews that raise questions about the frequency of use as well as the legal and ethical legitimacy of waivers. The potential for misuse is highlighted by specific cases. The purpose of the presentation is to spur a comparative discussion of relevant norms and regulations in Japan.
主たる世話人:武藤香織(公共政策研究分野)
世話人:神里彩子(生命倫理研究分野)
本日第8回公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:1月8日10時~12時半頃
| 発表者1: | 内山正登(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 客員研究員) |
|---|---|
| タイトル: | 2019年の研究活動の報告と博士論文の概要 |
要旨:
昨年一年間、これまで行ってきた受精卵を中心としたヒト生殖細胞系列へのゲノム編集に関する啓発プログラムの開発以外に、食品へのゲノム編集の利用に関する意識調査、遺伝分野における適切な用語のあり方に関する研究活動を進めてきた。それぞれ、学会発表と論文投稿というかたちでまとめることができた。そこでこれらの報告をするとともに、現在取り組んでいる博士論文の概要と進捗状況について説明する。
| 発表者2: | 須田 拓実(大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻医療イノベーションコース 修士課程) |
|---|---|
| タイトル: | Undocumented Immigrantsの医療へのアクセスに関わる諸課題について |
要旨:
発表者が昨年4月以降に主に取り組んできた内容を整理した上で、特に関心を持った上記のテーマについて調べたことと、今後の課題や発表者が調査・検討したいことを報告する。在留資格のない外国人(Undocumented Immigrants)に関して、医療の提供より取締を強化しようとする国々が見られる。例えば米国では、特に現在の政権下での移民政策において、連邦政府が主体となってUndocumentedImmigrantsを拘束し、国外追放する事案が多数ある。この動きに対して一部の州や医療機関では、在留資格を問わず外国人が必要とする医療を提供することで、ある種の「駆け込み寺」として機能するべく取り組まれている。日本では、2000年代の取締強化により、Undocumented Immigrantsの数は減少した。しかし、近年で国策として受け入れ数が急増している技能実習生を初めとして、在留資格を失うリスクを抱えた外国人は存在し、今後の増加も見込まれる。海外での議論を参考にしつつ、日本国内でUndocumentedImmigrantsに対しても医療へのアクセスを担保するために、発表者が今後取り組むべきと考えている課題を述べる。
東京大学医科学研究所 学友会セミナーのお知らせ
http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/events/gakuyukai/archive/post_872.php
| 開催日時: | 2020年1月20日(月)18:00~19:00 |
|---|---|
| 開催場所: | 総合研究棟8階 大セミナー室 |
| 講師: | 李 怡然 |
| 所属・職名: | 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 公共政策研究分野 特任研究員 |
| 演題: | 医療・医学研究に関する「告知」の研究―遺伝性腫瘍に関する家族内での情報共有を事例に |
概要:
2010年代以降、疾患の早期発見や予防・治療選択のために、医学的にactionable(対処可能)な疾患について、患者や家族が積極的にリスクを知り、家族内で共有することを、推奨する傾向が強まっている。たとえばBRCA1/2は遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)の原因遺伝子であり、サーベイランスや乳房・卵巣のリスク低減手術、分子標的薬PAPR阻害剤の選択のためにも、血縁者への情報共有が期待される。さらに、がんゲノム医療が推進され、網羅的なゲノム解析を伴うがん遺伝子パネル検査が臨床実装、保険収載された。つまり、家族歴をもたない一般のがん患者と家族も、二次的所見としてわかる遺伝性腫瘍の情報の取扱いについて、意思決定に直面する事態が生じている。しかし、日本の患者・家族の情報共有の実態や課題点については、十分明らかにされていない。
本研究では、がん患者・家族への質問紙調査を通して、がん遺伝子パネル検査で遺伝性腫瘍の可能性がわかった場合の、情報共有への希望を明らかにした。また、HBOC患者・家族へのインタビュー調査から、家族内でのコミュニケーションの態度や経験を考察した。
本セミナーでは、ほかの医療・医学の「告知」研究にも言及しつつ、遺伝情報に関する「リスク告知」研究の概要を紹介する。また、今後の展望として「知らないでいる権利」や医療者の守秘義務に関する近年の議論の動向、子どもの全ゲノム解析に関する論点について触れたい。
主たる世話人:宮野 悟(DNA情報解析分野)
世話人:武藤香織(公共政策研究分野)
本日第7回公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:12月11日10時~12時半頃
| 発表者1: | 楠瀬まゆみ(大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻博士後期課程) |
|---|---|
| タイトル: | 研究におけるベネフィットシェアリングに関する倫理的議論に関する検討 |
要旨:
研究倫理の文脈においてベネフィット・シェアリング(benefitsharing)の議論がなされ始めたのは比較的新しく、議論が十分になされていない
分野の一つである。従来、研究におけるヒト試料・情報の提供に関しては利他主義に基づいた無償提供が前提とされている。しかし、企業等のなかには、それら無償で得た情報を販売することによって利益を得ている場合もある。Schroeder(2006)は、ベネフィット・シェアリングを、交換の正義を達成するためにヒト遺伝資源提供者にその資源利用に由来する利益や利潤の一部を提供する行為と定義する。さらにAnderson & Schroeder(2013)は、ベネフィット・シェアリングの背後にある哲学的原則として、科学技術の研究や発展に貢献した人々は、その利益を共有するべき(oughtto)であると述べ、科学的進歩の貢献者と利益を共有しない場合の搾取の可能性について指摘している。そこで本発表においては、研究におけるベネフィット・シェアリングに関する基礎的文献からベネフィットシェアリングに関する根本をなす倫理的議論を概観する。
| 発表者2: | 河合香織(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース修士課程) |
|---|---|
| タイトル: | 遺伝的特徴における結婚差別とは何か |
要旨:
遺伝的特徴に基づく差別とは、科学的に解析あるいは検査されたゲノムの状態をも含む、遺伝的特徴に基づくあらゆる区別、排除、制限、又は優先である(厚生労働科学特別研究, 2017)。その中でも結婚をめぐって生じうる差別とは何かについて、修士論文として調査する。差別の形成にあたって、遺伝カウンセリング等の専門知を提供する遺伝医療の専門家の規範や差別意識が当事者の意識に反映する場合も少なくないと予想する。専門家を対象に、差別に関する教育歴、自身が形成した規範と臨床実践、クライアントからの相談内容と対応の事例など、質問紙調査とインタビュー調査を行うことにより、遺伝的特徴に基づく差別に関する知の蓄積に貢献したい。
私たちはこれまで、日本網膜色素変性症協会(JRPS)からご縁を頂き、本邦で初めてiPS細胞の臨床応用に挑まれた髙橋政代先生(理化学研究所・2019年7月迄)との対話の機会に恵まれてきました。その内容は、2014年7月28日に「共につくる臨床研究~患者と研究者の対話から~」という報告書として取りまとめました。
本邦では、2014年に滲出型加齢黄斑変性に対する自家iPS細胞由来網膜色素上皮(RPE)シート移植に関する臨床研究が実施され、その後も、複数の疾患に対する臨床研究が計画・実施されてきました。未知のリスクを伴う臨床研究であること、そして社会的な期待が過度に高まっていることなどを踏まえ、研究計画の立案段階から研究者と対象疾患の患者が対話をすることは必要であるとされています。再生医療分野では、臨床研究に関する啓発をしながら、研究計画や方向性への意見を陳情する取組みをJRPSが先駆けとなって実施してきましたが、こうした取組みは、今後、ますます重要なものになると考えられます。
このたび、網膜色素変性症(RP)に対する臨床研究の実施が近づいてきたことから、再びご縁を頂き、2018年11月18日に「JRPSワークショップ2018 in 神戸~網膜再生医療臨床試験・患者からのアプローチ~」をJRPSと共催させて頂くことになりました。今回も髙橋政代先生にご協力いただき、「臨床試験を成功させるために、患者は何ができるか、何をすべきかを考える」ことをテーマに、RP患者さんやご家族と一緒に考え議論しました。さらに、この企画は神戸会場と東京会場、札幌会場をオンラインでつなぐ3元中継の試みとして開催されました。本報告書は、この日の発言録をもとに、読者が追体験できるように再構成したものです。
この報告書冊子の入手をご希望の方は、
までお申し込みください。
報告書冊子のPDF版はここからダウンロードできます。
また、テキストデータもPDF版とword版の2種類をご用意しています。音声読み上げソフトの仕様等に合わせて、お好きなほうをダウンロードしてください。
テキストデータのPDF版はここからダウンロードできます。
テキストデータのword版はここからダウンロードできます。
※ この報告書作成にあたり、日本医療研究開発機構(AMED)「再生医療の実現化ハイウェイ」における、「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究」(課題D)より財政的支援を得ております。ここに御礼申し上げます。
本日第6回公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:11月13日10時~12時半頃
| 発表者1: | 高嶋佳代(大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻博士後期課程) |
|---|---|
| タイトル: | 患者対象のFIH試験における倫理的課題の検討 |
要旨:
治療法開発において初めて人を対象とするFirst in Human(FIH)試験では、安全性を確認することが主な目的となる。しかしながら、一般的な薬理試験でのFIH試験が健康な成人を対象とするのに対して、FIH試験の対象が患者である場合、リスクベネフィットのバランスを検討するのは容易ではない。その理由として、患者が対象となるFIH試験の場合、他に(標準)治療法がない場合があり、安全性のみならず、ある程度の治療的効果を期待することを一概に否定できないことが挙げられる。そこで本研究では、患者を対象として初めて試みる医療行為としてのFIH試験について理論研究を行い、その上でFIH試験に参加する患者自身の意識に着目して、患者自身によるリスクベネフィットの考え方や、FIH試験の意義などを考察したい。今回は、先月参加させて頂いたASBH(American Society for Bioethics and Humanities)で得た知識なども含めて研究の進捗に関する発表を行う。
| 発表者2: | 飯田寛(大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻博士後期課程) |
|---|---|
| タイトル: | 修士課程と博士課程の研究の状況 |
要旨:
修士課程で研究した「日本における生命保険と発症前遺伝学的検査をめぐる諸課題の検討」について、その後の学会誌への投稿状況等について報告する。博士課程においては労働分野におけるゲノム情報の取扱いに着目している。労働者の高齢化や少子化による労働者の減少の観点から事業者は労働者が健康で長く働くことを求めている。また、労働者もより長く働くことを望んでいる。この観点から労働者の職場の安全衛生や労働者の健康を管理する産業医の役割は今後益々重要である。一方で今般、ゲノム医療が本格的に開始されており、これにより自身のゲノム情報に接する労働者が今後増大することが予想される。事業者によるゲノム情報の利用は労働者に不利な帰結を生むとの懸念から、諸外国では法的な規制が設けられている(厚生労働科学特別研究2016)。また、事業者と雇用関係にある専属産業医の勧告権の行使には限界があるとの指摘もある(藤野2013)。そのようななか、2018年に労働安全衛生法が改正され、事業者による労働者の健康情報の取扱は、労働者の健康確保に必要な範囲に限られることがあらためて確認されるとともに、事業者には労働者の健康情報等の取扱規定整備を求めている。しかし、政省令においてゲノム情報への特別な言及はなく、産業医や健康保険組合がゲノム情報を取扱う可能性に関する議論が不十分である。そこで、博士課程の研究では特にゲノム情報の利用可能性がある治療と仕事の両立支援、健康増進、安全衛生という産業医と健康保険組合が関連する3つの領域で事業者の責務と労働者の不当な取扱いの間にどのような問題が起こっているのかの具体的な実態を把握し、労働分野を射程にしたゲノム情報の諸課題を整理する。
学術支援専門職員の神原です。
このたび、日本遺伝カウンセリング学会誌に下記の論文が掲載されました。
神原容子、竹内千仙、川目裕、持丸由紀子、佐々木元子、三宅秀彦
「成人期ダウン症候群において必要とされる情報提供と家族支援のあり方」
日本遺伝カウンセリング学会誌、第40巻3号、101-108頁(2019年10月)
ダウン症候群のある方々の平均寿命の延長に伴い、ダウン症候群のある成人に対する健康管理と合併症治療の重要性は増しています。
成人期のダウン症候群のある方とその家族を対象に開催した「大人のダウン症セミナー」において、参加者を対象に質問紙調査を行い、情報提供と家族支援のあり方について検討を行いました。
その結果、ダウン症候群のある方の親は、成人後の認知機能と認知症、情緒と行動異常などに高い関心があることが明らかになりました。
このような、セミナーの取り組みは、家族が望むダウン症候群に関する情報提供の役割を果たし、今後の情報提供の場として有用であると考えられました。
本日第5回公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:10月9日11時~12時頃
| 発表者1: | 北林アキ(大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻博士後期課程科) |
|---|---|
| タイトル: | 患者・市民の視点を踏まえた医薬品情報の提供を実現するための課題の検討 |
要旨:
医薬品は、品目毎に厚生労働省の承認を受けて初めて製造販売、すなわち市場に出荷又は上市できるようになる。しかし、承認前に得られる副作用等の情報は一般的に限られることに加え、2017年の条件付早期承認制度の開始等によって、承認後の情報収集の重要性が、副作用の早期発見や適正使用のために一層増している。収集する情報源として、これまで主であった製薬企業や医療者からの情報に加え、患者から寄せられる情報の利点が注目され始め、副作用の早期発見や適正使用のために当該情報を規制当局の意思決定に活用する取組みが世界的にも進んできている。しかし、こうした取組みが始まったのは2000年代初頭と比較的最近のことであり、未だ各国でも模索が続き、課題を抱えている状況である。そこでリサーチクエスチョンとしては、患者の実体験の情報を基に承認後の医薬品評価を行うという世界的な動向が、市民と医薬品行政の関係にどのような変化を求め、またそれはどのように可能なのか、ということを考案した。本報告にて、現在構想中の研究計画を共有することで、今後の調査研究の計画立案のための糧としたい。
治験については臨床研究中核病院等を中心とする中央治験審査委員会にて、また、「臨床研究法」に基づく特定臨床研究では認定臨床研究審査委員会にて中央倫理審査を行うための基盤整備が進められてきました。しかし、観察研究等の介入を伴わない研究(以下、非介入研究)に関しては、倫理指針で一括審査を認めているものの、その基盤整備はされてきませんでした。
そのため、AMEDでは平成30年度より非介入研究の中央倫理審査に向けた基盤整備が進められ、私たちも、本年度、基盤整備に向けた取り組みを行うことになりました。
中央倫理審査の実践においては、倫理審査の委託又は受託に関する手続きの多くを事務局が担うことになるため、その基盤整備において事務局の方のご意見は極めて重要と考えています。そこで、倫理審査委員会事務局の皆様にお集まりいただき、非介入研究の中央倫理審査を関するご意見をお聞かせいただくためのワークショップを企画しました。
当日は、平成30年度に「多機関共同非介入研究における倫理審査集約化に関するガイドライン」(案)を作成した東北大学病院 臨床研究推進センターの先生に同ガイドラインの解説もしていただく予定です。ご多忙とは存じますが、是非ともご参加くださいますようお願い申し上げます。
| 対象: | 倫理審査の委受託に関心のある倫理審査委員会事務局の方 (委受託経験の有無は問いません。未経験または経験の浅い事務局の方々も歓迎!) |
|---|---|
| 日時: | 2019年10月7日(月) 14:00~16:30(受付開始:13:30~) |
| 会場: | TKP品川カンファレンスセンター バンケットホール4J(品川駅から徒歩1分) |
| お申込み〆切: | 2019年9月27日(金) |
アリス・ウェクスラー氏(遺伝病財団理事)と若手研究者との交流研究会を開催します
【概要】
米国遺伝病財団の理事でいらっしゃるアリス・ウェクスラーさんを日本にお招きし、交流研究会を開催いたします。アリスさんは、ハンチントン病(HD)の当事者家族であり、また、歴史家としてHDに関する著作を多く執筆されています。研究会では、米国におけるHDの「発見」を描いた著作The Woman Who Walked in to the Sea: Huntington's and the Making of a Genetic Disease(Yale University Press; 2008)を題材に、お話いただく予定です。また、後半では、難病や遺伝性疾患をフィールドに調査を行っている日本の若手研究者から話題提供を行います。
ディスカッションを通じて、日米の患者会活動や科学コミュニティとの関わりについて、意見交換ができれば幸いです。
なお、報告とディスカッションは英語で行われます。
(※注:患者さん、ご家族、一般の方々が対象の講演会は別日程(9/29(日))で開催されます。ご関心のある方は、こちらをご覧ください)
Young Scholars with Alice Wexler Event
| 日時: | 2019年9月26日(木) 10時~13時頃 |
|---|---|
| 場所: | 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階 公共政策研究分野 セミナー室 (東京都港区白金台4-6-1) [アクセス・キャンパスマップ] |
| プログラム (話題提供者): |
司会者:Kaori Muto 武藤 香織 東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授 1)Alice Wexler 米国遺伝病財団 理事 2)Saori Watanabe 渡部 沙織 東京大学先端科学技術研究センター 人間支援工学分野 日本学術振興会特別研究員PD 3)Izen Ri 李 怡然 東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任研究員 |
| 対象: | 関心のある研究者の方々 |
| 参加方法: | 以下の「申込みをする」ボタンより事前にご登録ください。 |
| 主催: | 東京大学医科学研究所公共政策研究分野 |
| お問い合わせ: | 東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 E-mail: |
本日第4回公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:9月11日13時半~16時頃
| 発表者1: | 神原容子(東京大学医科学研究公共政策研究分野 学術支援専門職員) |
|---|---|
| タイトル: | 成人期ダウン症候群において必要とされる情報提供と家族支援のあり方について |
要旨:
ダウン症候群のある方々の平均寿命の延長に伴い、ダウン症候群のある成人に対する健康管理と合併症治療の重要性は増している。成人期のダウン症候群のある方とその家族を対象に開催した「大人のダウン症セミナー」の取り組みと、現在行っている研究内容について報告する。
| 発表者2: | 永井亜貴子(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任助教) |
|---|---|
| タイトル: | がん遺伝子パネル検査に対する患者・市民の態度に関する研究 |
要旨:
がん組織の遺伝子を一括して網羅的に調べるがん遺伝子パネル検査は、2018年4月より先進医療として実施され、有効性と安全性について検討が行われた。2019年6月からは、がん遺伝子パネル検査の2製品の保険適用が開始され、がんゲノム医療を実施する体制づくりが進められている。こうした状況の下、2018年に実施したがん遺伝子パネル検査に関するインターネット調査の回答者であるがん患者、がん患者の家族、市民を対象として、2019年8月に同検査に関するインターネット調査を行った。本報告では、がん遺伝子パネル検査を取り巻く状況が変化する中で、同検査に対する態度に変化があるかについて検討した結果を報告する。
特任研究員の船橋です。
このたび、「薬理と治療」に臨床試験法に関する以下の論文が掲載されました。
船橋亜希子、井上悠輔
臨床研究の「記録」に関する新しいルール ―臨床研究法をいかに理解し、いかに守るべきか?―
薬理と治療47巻Suppl 1, 37 - 41 (2019)
データ不正事案を背景に成立した臨床研究法は、データの「保存」義務に違反した場合に、50万円以下の罰則を設けています。
そこで、本稿においては、診療・研究に関する記録の保存に関する規制について整理・検討を行いました。
本稿に取り組む中で、改めて、臨床研究法の定義の問題、そもそもの理解の難しさ、それに伴う遵守の難しさを痛感し、そこから、副題をつけました。
倫理指針による規制から、臨床研究法という法律による規制に移行したことは、どのような波及効果を有するでしょうか。
今後の動きにも、引き続き注視する必要があると考えています。
講演会「医療・研究開発に意見を言える患者像を目指して ~欧州の取組みに学ぶ~」を開催します
【概要】
近年、諸外国では、医療・研究開発における患者・市民参画の推進が進められており、日本でも注目が高まっていますが、患者が学ぶ機会を確保することが課題となっています。欧州では、「欧州患者アカデミー」(European Patients' Academy on Therapeutic Innovation(EUPATI))という、医薬品の研究開発に関する患者の知識向上を目的とした教育資材が開発され、多くの卒業生を輩出しています。日本でも、患者が知識や役割を学び、多様な経験を生かしつつ、活動できる環境を整えることが必要です。そこで、欧州での取組みを学ぶため、「欧州患者アカデミー」から専門家をお招きして、講演会を開催することとなりました。ぜひふるってご参加ください。
| 日時: | 2019年9月7日(土) 14時~16時(開場13時30分) |
|---|---|
| 場所: | 東京大学医科学研究所1号館講堂 (東京都港区白金台4-6-1) [医科研アクセスマップ] [医科研キャンパスマップ] |
| プログラム: | 1)講演 講師:マシュー・メイさん 欧州患者フォーラム(European Patients' Forum) プログラム・コーディネーター |
| 2)質疑応答 | |
| 対象: | 関心のある患者さん、ご家族、一般の方々 |
| 参加方法: | 参加費無料。以下の「申込みをする」ボタンから事前の参加申込が必要 |
| 通訳: | 遂次通訳のご用意があります |
| 主催: | 東京大学医科学研究所公共政策研究分野(AMED「再生医療の実現化ハイウェイ再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究(課題D)」) |
| 共催: | 患者・市民参画コンソーシアム |
| お問い合わせ: | 東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 E-mail: |
アリス・ウェクスラー氏(遺伝病財団理事)講演会を開催します
【概要】
アリス・ウェクスラーさんは、HD(ハンチントン病)の当事者家族として国際的に著名であり、歴史家としてHDやご自分のご家族に関する数々の著作を執筆されています。また、アリスさんのお父様が創設された、遺伝病財団(Hereditary Disease Foundation)は、1970年代から基礎研究者への投資を開始し、今日の米国の患者団体のモデルとなりました。このたび、アリスさんを日本にお招きすることになりました。難病の当事者が閉じこもらず、科学や社会と積極的に関わりながら生きること、歴史的にみたHDなどについて、お話をしていただきます。
※ HD(ハンチントン病)は、常染色体優性遺伝の神経変性疾患です。この疾患は、欧米の優生政策において重要な標的となった過去をもつ反面、ヒトゲノム解析研究が開始されたときにはHDの当事者が倫理的法的社会的課題を考えるグループのリーダーとなったり、幹細胞治療研究でもHDを対象とした取組みが早々に実施されるなど、難病の研究開発において様々な経験をしてきました。日本でも指定難病となっています。
| 日時: | 2019年9月29日(日) 14時~16時(開場13時30分) |
|---|---|
| 場所: | 東京大学医科学研究所1号館講堂(東京都港区白金台4-6-1) [医科研アクセスマップ] [医科研キャンパスマップ] |
| 対象: | 関心のある患者さん、ご家族、一般の方々 |
| 参加方法: | 参加費無料。以下の「申込みをする」ボタンから事前の参加申込が必要 |
| 通訳: | 遂次通訳のご用意があります |
| 主催: | 東京大学医科学研究所公共政策研究分野(AMED「再生医療の実現化ハイウェイ再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究(課題D)」) |
| 共催: | 日本ハンチントン病ネットワーク |
| お問い合わせ: | 東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 E-mail: |
本日、2019年度、第3回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:7月10日(水)13時半~15時頃
| 発表者: | 李怡然(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任研究員) |
|---|---|
| タイトル: | 家族内における遺伝性がんの「リスク告知」に関する研究 |
要旨:
がんゲノム医療の推進に伴い、疾患の早期発見や予防、治療薬の選択のために、疾患の発病リスクを家族内で情報共有すること(「リスク告知」)が医療者から推奨されるようになっている。遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)は、医学的にactionable(対処可能である)とされる代表的な遺伝性がんであり、診断を受けたもしくは疾患の疑いがある患者から血縁者に「リスク告知」を行うことがますます期待されると考えられる。では、患者はどの程度、家族と遺伝学的なリスクや遺伝学的検査に関する情報を共有しようとしているのか。また、伝えるかどうかの選択にはどのような背景や、課題があるのか。
本研究では、上記の問題意識を出発点に、HBOC患者と家族へのインタビュー調査を実施している。本報告では、現在取り組んでいる博士論文の全体の構想を示した上で、これまでに実施した調査の結果の中から、「リスク告知」に関する語りに着目して、報告を行う。
本日、2019年度、第2回目の公共政策セミナーが開かれました。
ゲストスピーカーの方にもお越しいただきました。
内容は以下の通りです。
◆日時:6月12日(水)13時半~16時頃
| 発表者1: | 船橋亜希子(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任研究員) |
|---|---|
| タイトル: | 最先端医療における刑事過失責任を考える |
要旨:
2017年度より「がんゲノム医療」という最先端の医療におけるELSI研究に携わったことを契機に、最先端医療と刑法の接点の模索と検討を繰り返してきた。当該活動における自身の一つの到達点が、伝統的な論点への回帰と再検討の必要性であった。そこで、当該課題に関するこれまでの取り組みと、現在行っている研究内容について、刑事医療過誤に関する研究内容も振り返りながら、報告する。
| 発表者2: | 中田はる佳(国立がん研究センター 社会と健康研究センター生命倫理・医事法研究部 研究員) |
|---|---|
| タイトル: | 未承認薬へのアクセス方法に関する日米比較 |
要旨:
保険診療によるがん遺伝子パネル検査の導入や、人工知能技術による治療法選択の拡大により、患者が未承認薬の利用を検討する機会が増加することが見込まれる。未承認薬の利用方法として、日本では2016年から拡大治験と患者申出療養制度が導入されている。一方、米国では、従来からあったFDAのExpanded access programに加えて、いわゆるRight-to-try法が導入され、2018年5月末には連邦法が成立している。本報告では、日米の未承認薬利用制度を概観した上で、患者団体のウェブサイト調査の結果を紹介し、未承認薬利用に関する情報の普及について検討する。
厚生労働省より、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」について、各都道府県の関係主管部局宛に通知が発出されました(社援発0603第1号、社援保発0603第2号、障障発0603第1号、老振発0603第1号)。これは武藤が分担研究者として参加した、平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」班(研究代表者 山梨大学大学院総合研究部医学域 社会医学講座 山縣 然太朗教授)の研究班の成果の一部です。
様々な方々の調査協力を得て、成年後見人できること、身元保証人(ビジネス)に頼らなくてもできることを整理し、成年後見人制度をはじめとする諸制度との調整も経てまとめられたものです。このガイドラインのご紹介ご批判もかねた事例検討会など、ぜひ多職種での対話の機会を増やしてくださいませ! ぜひご覧下さい。