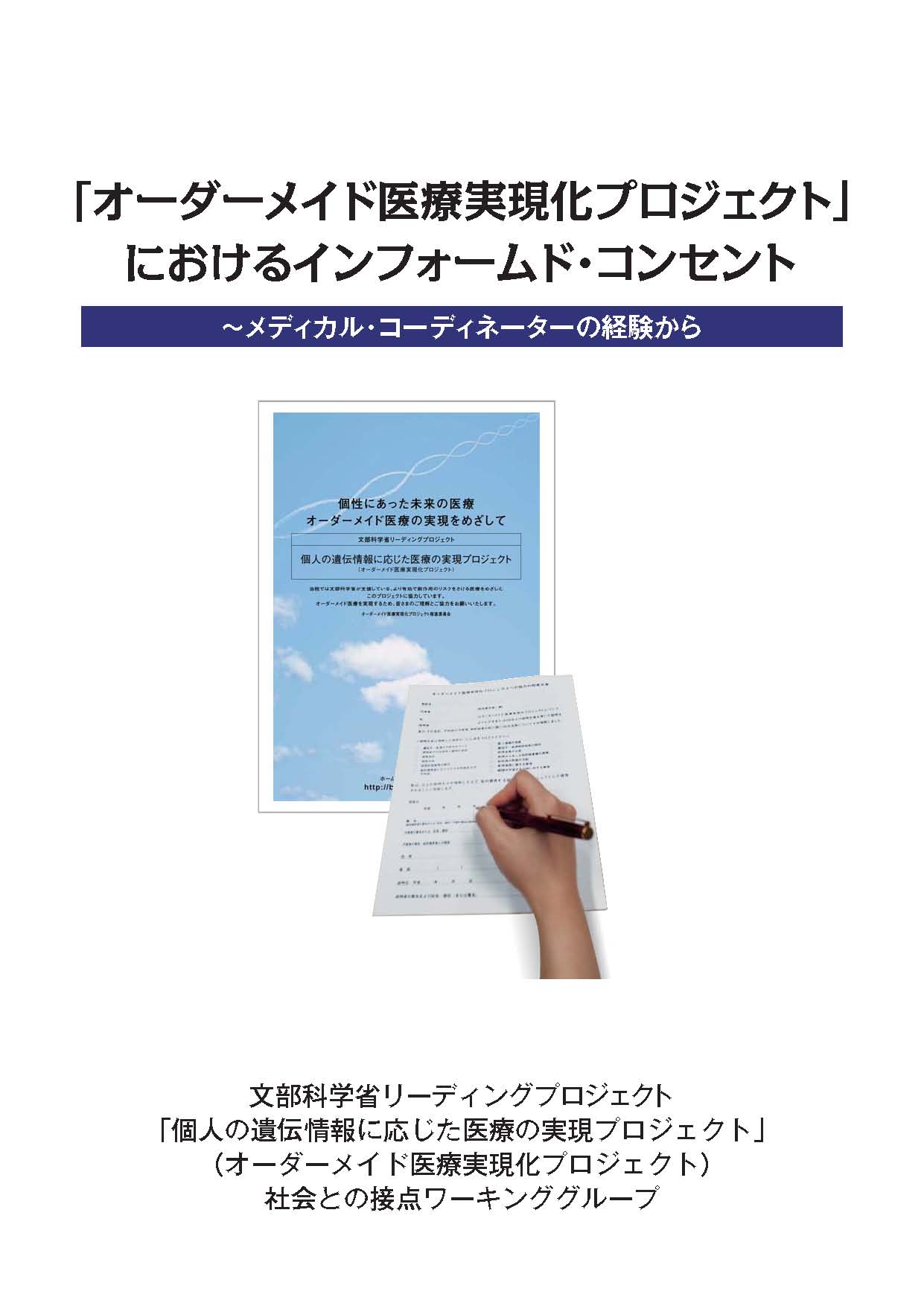第32回(2013年6月21日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
中田:
High-profile research & the media. The case of the AbioCor artificial heart.
E. Haavi Morreim
Hastings Center Report. 2004 Jan-Feb;34(1):11-24.
趙:
我国遗传服务和出生缺陷干预相关问题探讨
(Issues of Genetic Services and Birth Defects Intervention)
睢素利(SUI Su-li)
Chinese Medical Ethics. Apr. 2013 Vol. 26 No. 2
梅雨や台風で不安定な天気が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。院生室(通称3研)には扇風機や虫除けマット、麦茶など夏のものが準備されつつあります。
今回は、私が参加してきた海外学会のご紹介です。6月12日から15日まで、シカゴで開催された米国人工臓器学会(American Society for Artificial Internal Organs: ASAIO(アサイオと呼ばれます))に参加してきました。この学会は、人工臓器の研究開発や臨床使用に関連する人々が集まる学会で、参加者のバックグラウンドは医学、工学、生体工学、看護などさまざまです。今回の参加の目的は、私自身が取り組んでいる医療機器×倫理というテーマでの発表場所を探すことと、アメリカにおける医療機器研究開発の現状を少しでも把握することでした。
学会初日は、小児用デバイスに特化した分科会のようなもの(PEDIATRIC MECHANICAL CIRCULATORY SUPPORT PROGRAM)が開かれていました。ここでは、小児用デバイスに関する政府の取り組みや、臨床試験の進捗状況などが発表されていました。特に、FDAやNHLBI(米国心臓、肺、血液研究所。NIH傘下の国立研究機関)など政府関連の機関の取り組みを興味深く聞きました。
翌日からは、学会の本会が始まりました。事前に公表されていたプログラムで、聞きたいセッションや見たいポスターの目星をつけていたので、それらを中心に回りました。補助人工心臓(ventricular assist device: VAD)装着患者・家族の教育に関する研究や、機械的循環補助(mechanical circulatory support: MCS)を受けている患者に対するインタビュー調査、病院で人工肺を使用した際のコスト計算をした研究など、人工臓器の研究開発・臨床使用を取り巻く社会的な課題にアプローチしたものがいくつか見られ、自身の今後の発表の参考になりました。また、プレゼンテーターが全員FDA関係者というFDA Sessionが設けられており、医療機器開発のイノベーションにおける課題、FDAの取り組みなどが紹介されていました。日本は医療機器開発のイノベーションが起こりにくい、規制が厳しい等よく言われるところですが、このセッションを聞く限りでは、アメリカでも自国の状況について同じような問題意識を持っていることが伺えました。FDA関係者は現地に来ることがなかなか難しいのか、ウェブ会議システムを用いての発表が多かったのですが、それでも多くの関係者が学会で発表し、現場の研究者等と意見交換をする試みは有益であると思いました。その他、VADコーディネーターが集まるセッションなどにも参加し、実り多い学会でした。
学会の合間には地のものを楽しもう、ということでシカゴ名物deep-dish pizzaを食べに行きました。
各種地ビールとともにいただきます。
一切れでギブアップしました。


学会に参加することで研究内容の情報収集だけでなく、発表方法なども自身の参考になることが多くあります。今後も機会を見つけて積極的に参加したいと思います。
(D2・中田はる佳)
公共政策研究分野は、文部科学省の「個人の遺伝情報に応じた医療実現プロジェクト(オーダーメイド医療実現化プロジェクト)」の社会との接点・ワーキンググループとして、プロジェクトの広報および倫理的な支援活動を行っています。その活動のひとつとして、「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」がIC担当者として養成したメディカル・コーディネーター(MC)に着目し、ゲノム医科学研究におけるインフォームド・コンセント(IC)の実践について調べました。病院で長時間の順番待ちで疲れている患者さん(試料提供者)への負担を軽減するために、MCの方々がどのようなリスク管理をし、配慮をしているのか、また、患者さんとの信頼を築くためにどのようなコミュニケーションをしているのか、その詳細について、MCさんの語りから分析しました。今後さらに注目していきたいのは、MC業務の専門性です。IC実践において、研究者側や患者さん側からMCに期待される役割は、可視化できない部分が多いため、MCの役割をどのように規定し、専門的領域を構築していくべきなのかについて、今後、他職種との比較分析をすえながら考察していきたいと思います。
○本報告書をご覧になりたい方は、こちらへ→
★PDF統合版ダウンロード(8.2MB)
※統合版をダウンロードする際には、ファイルが重いのでご注意ください。
★PDF3分割版
・Part1ダウンロード(2.1MB)
・Part2ダウンロード(5.8MB)
・Part3ダウンロード(1.7MB)
○第1期の説明同意パンフレットをご覧になりたい方は、こちらのサイトからご覧いただけます。
○第3期の説明同意パンフレットをご覧になりたい方は、こちらのサイトからご覧いただけます。
最近、医科研で研究をしている外国人研究者が増えています。日本語が話せない外国人は少なくなく、日常会話には英語が共通語として使われています。一方、日本の科学界や経済界は英語が堪能な人材を望んでいます。そのため、日本の学生たちは海外文化に触れ、英語で外国人と交流できるようになりたいと考えています。外国人研究者たちも日本の学生と楽しく交流をしたいと考えています。こうした双方の希望が合致して、「イングリッシュディナー」が生まれました。
このアイデアは、最近瀧尻崇史さん(発生工学研究分野、修士2年)が発案しました。毎週月曜日の19時半から医科研食堂に集まり、夕飯をたべながら自由に英語で話します。いろいろな国籍の学生が十人ぐらい参加しています。出欠は自由です。時々英語の意味が通じないことがありましたが、みんなが楽しんで交流していました。
多くの学生は、小さい頃から外国語を勉強しています。いろいろな英語勉強方法をさがして学んでも、なかなか英語が話せない人が少なくないです。これは、ふだん覚えた英語を口に出さないからだと思います。この「イングリッシュディナー」のような交流会は英語を話す機会が少ない学生たちによい場だと思います。
(M2・趙斌)
本日、2013年度、第2回目の公共政策セミナーが開かれました。
詳細は、以下の通りです。
| 日時: | 6月5日(水)10時~12時 |
|---|---|
| 報告者: | 小林智穂子(学際情報学府修士課程) |
| タイトル: | 日本企業の“社会貢献”活動 |
概要:
修士論文では、文献調査と事例検討を通じて、日本企業が実施してきた社会貢献活動を歴史的に整序するとともに、日本企業による社会貢献活動の実情や特徴を浮き彫りにしたうえで、今後の課題を模索しています。
発表は、その中間報告を行います。
ウプサラにも春が来ました。種々の花が一斉に咲き、木々の緑もすっかり濃くなりました。通学路は、人に臆せぬ鳥のさえずりに満ちています。緯度が高いので(約60度、東京は約35度)、まだ外が明るいと思って油断していると、夜の10時ごろだったりします。月末の夏至祭に向けて日照時間はまだまだ長くなります。
今は人の入れ替わりが多い時期です。最近のセミナーでは、新たに雇用される研究員の方々による研究紹介や、院生さんの進捗の発表が多いです。進行の形式は、私が日本で経験したものと大きな違いはないのですが、スライドを用いる場合のほか、院生さんの場合には、執筆中の原稿について意見を出し合うというものも多いように思われます。これとは別に、隣の部屋の哲学者がこつこつと書き溜めているセンターのブログがあります。先日、彼に頼まれて、日本の新しい公衆衛生法規に関する文章を寄せました。関心のある方はこちらからどうぞ。
ところで先週には学位授与式の日がありました。授与者を満載したにぎやかなオープントップバスが市内を練り進んでいました。また、ウプサラでは、式当日に軍が授与者の数だけ祝砲を打つことが慣例となっています。
ウプサラはやや特異な場所だとしても、一般にスウェーデンでは、学術研究への社会の信頼が高いとされています。例えば、重要な法案の審議や政策立案においては、学識者の意見を聞く段階が設けられますし、医学研究においても学術研究への試料の利用に異論を唱える声は限られてきました。しかし、個々の学識者についていえば、それらの発言力は過小に評価されることもなければ、過大に評価されているわけでもなく、個々人の専門性に関して淡々と受け止められている観があります。契約外の労務に動員されることもなければ、一方で、専門分野以外にも影響力を有するようなカリスマ性も期待されていないというところです。
一方で、学識者が実務作業や社会に対して持つ視点も、どことなくドライなものを感じます。例えば、スウェーデンの医療体制は現在、深刻な状況に直面しています。しかし、これまで大学研究者による問題提起は活発でなかったように思います。先日のストックホルムでの焼打騒動は日本でも紹介されたようですが、このあたりも行政の仕事ということで淡々と受け止められているように思うのです。暗黙の距離感というか、役割分担のようなものがあるのかもしれませんが、よく分かりません。こちらで滞在を始めてから何となく感じ続けてきたことなので、書いてみました。
写真:ウプサラ駅前。暖かくなったので、日向ぼっこをする人、日光浴をする人をよく見かけます。
(井上:ウプサラ大学にて在外研究中/スウェーデン王国)
2013年6月1日(土)
オープン・ラボ
| 時間: | 11時~15時 |
|---|---|
| 場所: | 公共政策研究分野研究室(白金台キャンパス) |
大学院進学に関するご相談をラボでお受けします。事前にご連絡をいただければ、大変うれしいですが、当日訪問でも構いません。お気軽にお越し下さい。
2013年6月1日(土)
大学院学際情報学府入試説明会
「各研究室のブース展示と研究紹介」にも参加します
| 時間: | 16時~17時 |
|---|---|
| 場所: | 東京大学本郷キャンパス福武ホール 地下二階ラーニングシアター 地下鉄丸の内線・大江戸線[本郷三丁目駅]から徒歩8分 地下鉄南北線[東大前駅]から徒歩8分 |
ご都合により、以上の行事に参加できない場合には、お問い合わせください。
なお、今年度の入試に関して、受験を検討される方からのご相談を受けられる期間は、出願前までとなっております。
■新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻を受験される方は、6月20日(木)まで
■大学院学際情報学府文化・人間情報学コースを受験される方は、7月15日(月)まで
ご注意ください。
博士課程2年の中田はる佳です。
しばらく更新が止まっていた「院生室より」ですが、今年度からは院生も6名になり、様々なバックグラウンドを持つ学生が集まるようになったので積極的にいろいろなことを発信していきたいと思います。
さて、2013年度の1本目は、ちょっと変わった私の博士課程研究生活についてご紹介したいと思います。
公共政策研究分野には主に院生たちが集っている部屋(通称「3研」)があるのですが、普段はそこにはおらず、大阪の国立循環器病研究センターで非常勤研究員として勤務しています。このセンターは、循環器疾患の抑圧を目標として設置されたナショナルセンターで、特に医療機器の研究開発に力を入れており、いわゆる医工連携を肌で感じることができます。私は現在「医療機器と倫理」をキーワードに研究を進めており、格好の研究フィールドとなっています。
東京の研究室に所属して、普段は大阪にいるの?いつ研究室に行くの?とよく不思議がられますが、白金台の「3研」には、第一・第三金曜日に行われる教室ミーティングとジャーナルクラブ、月に一回行われる公共政策セミナーのときにやってきます。その機会を利用して、研究相談や進捗報告をしたり、外部の方を交えて研究ミーティングをしたりしています。また、この時が他の院生や研究員の人たちと直接情報交換ができる貴重なときでもあります。
博士課程1年目は研究計画を具体的に詰める、という「考える」作業であっ?!という間に過ぎました。今年度は博士論文用のデータ収集・分析を進めることと、それとは別に論文を1本書き上げるという「手を動かす」ことが目標です。まだ2013年度が始まったばかりですが、長いようで短い1年間になりそうです。
(D2・中田はる佳)
第31回(2013年5月17日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
神里:
「第一部表象される身体<理論編>」
浮ヶ谷幸代
「身体と境界の人類学」(2010年)春風社
礒部:
「第9章 ワークショップの評価」
高木光太郎
苅宿俊文、佐伯 胖、高木 光太郎 編「ワークショップと学び3 まなびほぐしのデザイン」(2012)東京大学出版会
中田:
Failure Mode and Effects Analysis as an Informed Consent Tool for Investigational Cardiothoracic Devices
Katrina A. Bramstedt
ASAIO Journal. 2002 May-Jun; 48(3):293-295
趙:
Second Opinions: The Old Eugenics and the New Genetics Compared
Merryn Ekberg
Social History of Medicine Vol. 20, No. 3 pp. 581-593
岩本:
Male microchimerism in the human female brain
William F. N. Chan, Cécile Gurnot, Thomas J. Montine, Joshua A. Sonnen, Katherine A. Guthrie, J. Lee Nelson
PLos One. 2012;7(9):e45592. 2012 Sep 26
江:
Use of Complementary and Alternative Medicine Among Patients with Cancer Receiving Outpatient Chemotherapy in Taiwan
Che Yang, Li-Yin Chien, Chen-Jei Tai.
The Journal of Alternative and Complementary Medicine. May 2008, 14(4): 413-416.
本日、2013年度、第1回目の公共政策セミナーが開かれました。
詳細は、以下の通りです。
| 日時: | 5月7日(水)10時~12時 |
|---|---|
| 報告者: | 磯部太一(公共政策研究分野特任研究員、日本学術振興会特別研究員) |
| タイトル: | 萌芽的科学技術ブレイン・マシン・インターフェースについてのアップストリーム・エンゲージメントの枠組み構築に関する研究 |
概要:
博士課程で行った一連の研究について報告します。具体的な内容としては、以下の通りです。脳神経科学の中で萌芽的技術であるブレイン・マシン・インターフェース(BMI)はリハビリ応用など社会への利益が期待される一方で、倫理的・社会的課題も指摘されています。このような技術について、社会に実装される以前の研究開発中の現段階において、社会への導入を見越して、不利益最小化・利益最大化を促進するための方策として、非専門家アクターが関与するアップストリーム・エンゲージメントの枠組み構築と実践を行いました。
厚生労働省の研究班で、遺伝性神経難病に関心を寄せているメンバーが集まり、遺伝学的検査に関して神経内科専門医がどのように考えているのかについて、意識調査を行いました。その結果が、「臨床神経」に掲載されました。神経学会会員の方は、こちらからどうぞ!
特に、家族性アミロイドポリニューロパシー(FAP)、ハンチントン病(HD)、筋強直性ジストロフィータイプ1(DM1)を対象にした遺伝学的検査への対応の違いなどが注目され、なんらかの対応が可能だと医師が考える疾患については、積極的に実施されていることがうかがえます。
なお、この論文の内容は、第37回日本遺伝カウンセリング学会にて、2013年6月23日に大畑尚子先生が口頭発表する予定です。
また、J-Stageから読むことが可能です。
神経内科専門医の遺伝子診断に対する意識調査
吉田邦広*,大畑尚子,武藤香織,土屋敦,澤田甚一,狭間敬憲,池田修一,戸田達史
*Corresponding author: 信州大学医学部神経難病学講座〔〒390-8621 松本市旭3-1-1〕
我が国における神経疾患の遺伝子診断(遺伝カウンセリング、遺伝子検査)の現状を把握し、今後のよりよい臨床応用のあり方を検討する目的で、神経内科専門医を対象とした遺伝子診断に対する意識調査を実施した。日本神経学会の協力をえて、神経内科専門医4,762名に対して調査用紙を配布し、1,493名(31.4%)から回答があった。神経内科医はおおむね疾患の特性や患者・家族の状況に応じて適切に遺伝子診断をおこなっていると思われたが、ガイドラインはあまり活用されておらず、遺伝子診断により生じえる種々の問題点に対する認識は必ずしも十分とはいえなかった。
(臨床神経, 53:337-344, 2013)
keywords:遺伝子診断,ガイドライン,遺伝カウンセリング,インフォームド・コンセント,心理社会的支援
第30回(2013年4月19日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
武藤:
HeLa publication brews bioethical storm
Ewen Callaway
Nature. 27 March, 2013
中田:
Innovation in Human Research Protection: The AbioCor Artificial Heart Trial
E. Haavi Morreim, George E. Webb, Harvey L. Gordon, Baruch Brody, David Casarett, Ken Rosenfeld, James Sabin, John D. Lantos, Barry Morenz, Robert Krouse, Stan Goodman
The American Journal of Bioethics. September/October 2006, Volume 6, Number 5
人工心臓で60日間延びる命の意味(上)
Michelle Delio
2001年07月06日
人工心臓で60日間延びる命の意味(下)
Michelle Delio
2001年07月09日
趙:
Mitochondria replacement consultation: Advice to Government
Human Fertilisation and Embryology Authority
March 2013
岩本:
Brazilian psychiatric brain bank: a new contribution tool to network studies
K. C. de Oliveira, F. G. Nery, R. E. L. Ferreti, M. C. Lima, C. Cappi, A. Machado-Lima, L. Polichiso, L. L. Carreira, C. Ávila, A. T. D. L. Alho, H. P. Brentani, E. C. Miguel, H. Heinsen, W. Jacob-Filho,C. A. Pasqualucci, B. Lafer, L. T. Grinberg
Cell and Tissue Bank June 2012, Volume 13, Issue 2, pp 315-326
★東京大学医科学研究所 大学院進学説明会
2013年4月20日(土) 医科学研究所講堂にて開催します。
17時頃から説明します。
★新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻 入試説明会
2013年5月11日(土) 本郷キャンパス 武田先端知ビル5F武田ホールにて開催します。
14時半頃から説明します。
★オープン・ラボ
2013年5月12日(日)11時~18時
2013年6月1日(土)午後予定
学際情報学府からの進学希望者の方も歓迎します。
事前に、
までご一報いただけるとありがたいですが、当日、いきなり訪問でもOKです。どうぞお気軽にお越し下さい。
第29回(2013年4月5日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
神里:
Stem cells cruise to clinic
David Cyranoski
Nature vol.494,27 February 2013 Corrected: 08 March 2013
洪:
出生前診断の受検に関する意思決定についての文献レビュー―意思決定の特徴とその要因から看護の方向性を考える―
山岡由季、臼井雅美、坂梨薫
母性衛生 2013, 第53卷4 号,pp.564-572
新型出生前診断、民間企業があっせん…米に検体
読売新聞 2013年3月29日
新型出生前診断始まる…認定15施設を公表
読売新聞 2013年4月2日
中田:
Ethics, economics and the regulation and adoption of new medical devices: case studies in pelvic floor surgery
Sue Ross, Charles Weijer, Amiram Gafni, Ariel Ducey, Carmen Thompson, Rene Lafreniere
BMC Medical Ethics.2010,11:14
小林:
産業材企業の地域貢献―YKKのブランディングをケースとして―
北島啓嗣
日本経営倫理学会誌 第17号、pp.275-285(2010年)
2013年4月より、日本学術振興会特別研究員(PD)として、礒部太一さん
特任研究員として、吉田幸恵さん
新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻修士課程1年生として、岩本八束さん・江念怡さん
をお迎えしました。どうぞよろしくお願い申し上げます!
第28回(2013年3月15日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
神里:
米国生命倫理委員会報告書に基づく幹細胞研究の体細胞と生殖細胞の分類基準
額賀淑郎
生命倫理22巻(2012年)22-23頁
中田:
Ethical aspects in trials of implantable medical devices
Paul S. Heckerling
JAMA,2003;290(12):1579
本日、2012年度、第10回目の公共政策セミナーが開かれました。
詳細は、以下の通りです。
◆日時:3月6日(水)10時~12時
| 第一報告者: | 永井亜貴子 (医科学研究所公共政策研究分野特任研究員) |
|---|---|
| タイトル: | オーダーメイド医療実現化プロジェクトの概要と臨床情報の解析 |
概要:
遺伝情報をもとにした個別化医療の実現を目指し、2003年より実施されている「オーダーメイド医療実現化プロジェクト」の概要と、収集された臨床情報の解析について報告します。
| 第二報告者: | 井上悠輔 (医科学研究所公共政策研究分野助教) |
|---|---|
| タイトル: | ウプサラ大での活動報告 |
内容:
11月からの在外研究について、現地の状況と活動の進捗について中間報告をします。
第27回(2013年2月28日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
洪:
日本の医療現場における患者向け説明文章の実態とヘルスリテラシー研究の課題
酒井由紀子、三田図書館・情報学会研究大会 2007年
神里:
Qualitative thematic analysis of consent forms used in cancer genome sequencing
Clarissa Allen, William D Foulkes
BMC Medical Ethics 2011, 12:14
楠瀬:
Helsinki discords: FDA, ethics, and international drug trials
Jonathan Kimmelman, Charles Weijer, Eric M Meslin
The Lancet, Vol 373, Issue 9657, pp.13-14, 3 January 2009
中田:
Decision-making in stem cell trials for spinal cord injury: the role of networks and peers
Marleen Eijkholt, Brian K Kwon, Ania Mizgalewicz, Judy Illes
Regenerative Medicine. Vol.7, No.4, pp.513-522, July 2012
入江:
神経画像研究における偶発的所見の対処法をめぐる倫理的問題―論点整理と考察
林 芳紀
「応用倫理」(北海道大学大学院文学研究科応用倫理研究教育センター)、第4号、2010年、pp.29-43
私事ではございますが、2013年2月1日付で、教授を拝命致しました。
公共政策研究分野をつくって頂いてから丸6年が過ぎようとしていますが、医科研の研究者の方々が、同じ仲間として受け入れて下さったことに、心から感謝しております。しかし、過分なご祝辞を頂く中で、学校教育法をあらためて読むと、この身分は大変に責任の重いことで、医科研の方々が新たな賭けをなさったように感じ、身が引き締まる思いです。
加えて、先行き不透明なこの研究室に、意を決して、心優しく優秀なスタッフや学生たちが集ってくれたことにも、感謝の気持ちでいっぱいです。医科研で、ひいては医科学研究コミュニティにおいて、この研究室の存在と役割を認めて頂けたのは、ひとえにみんなの力のおかげです。本当にありがとうございます。
2000年代から、医科学には経済効果やイノベーションが待望されるようになり、国の委託事業として契約の対象や、民間企業から投資の対象となってきました。そのようななか、私たちは、医科学研究者ではない立場の視点、病や障害とともに生きる方の視点を忘れないように心がけながら、主に研究倫理支援業務と倫理的・法的・社会的課題(ELSI)の研究を進め、わずかながら若い人材も育成してきました。また、最近では、附属病院看護部の皆さんと、臨床倫理を考える機会を頂いています。そして、国からは、ナショナルプロジェクトでの研究倫理支援業務を委託されるようになりました。
ただ、これは、たまたま時代の流れに合っていた、ということだろうと理解しています。本当に生き残れるかどうか、勝負はこれからです。
今後10年間、この研究室は、どのような役割を果たしていくべきなのでしょうか。医科学に対する「日本再生の旗頭」としての期待は、かつてないほど高まっています。しかし、そのペースに呑まれ、振り回され、ただ「支援」するだけでは、この研究室は自滅するでしょう。私たちは、医科学を間近に見守る者として、新たな関与のモデルをつくり、光の当たりにくいところに眼差しを向け、得られた知見を発信していかなければならないと思います。
考えながら走ることを許してくれる雰囲気は、医科研のよさだと思っておりますが、先頭を走らないと、きっと許してもらえないでしょう。皆様のご支援を得ながら、新たな覚悟とともに、邁進していきたいと考えております。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。
第26回(2013年2月1日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
洪:
卵の幹細胞をめぐる攻防
Trisha Gura
Nature ダイジェスト February 2013,Vol 10 No 2
神里:
Triggers for Research Ethics Consultation
Molly Havard , Mildred K.Cho, David Magnus
Science Translation Medicine 25 January 2012 Vol 4 Issue 118
趙:
中国における障害児童のニーズ分析―中国障害者連合会調査結果を通して
呂 暁彤
帝京科学大学紀要 Vol.8 (2012) pp.121-125