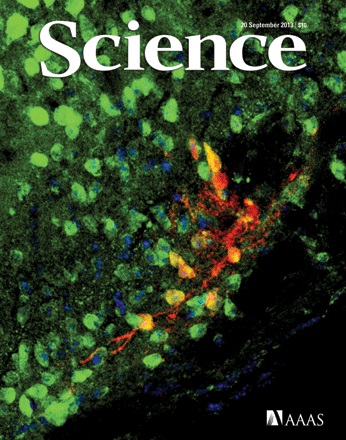第37回(2013年10月04日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
武藤:
Actionable, pathogenic incidental findings in 1000 participants' exomes
Michael O. Dorschner, et al.
The American journal of human genetics 93, 631-640, October 3, 2013
中田:
Cross the road
Editorials
Nature. 502(7469):6, 2013
臨床研究の倫理(研究倫理)についての基本的考え方
松井健志
医学のあゆみ Vol.246 No.8 2013.8.24
趙:
我国第一部地方性优生法规诞生——甘肃省制定禁止痴呆傻人生育法规
屈维英,牛新莉
瞭望 1989年4期
从甘肃看痴呆傻人生育问题的严重性
维新
瞭望 1989年4期
Chinese region uses new law to sterilize mentally retarded
Nicholas D. Kristof
The New York Times Nov.21 1989
岩本:
Public perceptions of animal experimentation across Europe
Fabienne Crettaz von Roten
Public Understanding of Science 22(6) 691-703. 2012
江:
台灣地區基因檢測態度調查與結果分析
何建志、陳李魁
法律與生命科學 第三卷第二期 Vol.3 No.2 April 2009
世界医師会によるヘルシンキ宣言は、研究倫理に関する最も重要なガイドラインの一つです。この宣言は現在、改訂作業中です。井上はウプサラ大学の仲間と議論のうえ、世界医師会の意見募集に応じてコメントを出しました(2013年7月)。その後、このコメントの一部をレターとして組み直して投稿したものが、サイエンス誌の今週号に掲載されました。
医薬品の試験におけるプラセボ使用の可否や倫理審査の質の課題など、研究倫理において従来取り上げられてきた論点が、今回の改訂をめぐる議論にも多く登場しています。ただ我々は、これまであまり論じられてこなかった試料・データの取り扱いに関する項目の変更にも関心を持っています。
2000年の改訂以降、ヘルシンキ宣言には、その射程とする医学研究に「個人を特定できる試料・データを用いる研究」が含まれることが明記されるようになりました。一方で、既存の試料・データを集合的に管理し、解析する研究形式の発展と、これらが由来する個人の自己決定権を尊重する観点とを考慮して、同意原則の適用のあり方をめぐる多様な議論が展開しています。
現在の改訂案では、同意取得要件の例外として認められてきた、「倫理審査により、研究の妥当性に深刻な影響があることが確認された場合」に関する記述が削除され、個人からの事前の同意取得の履行をより前面に出したものになっています。我々は、リスク・ベネフィットの比較衡量の観点から、この改訂作業の動向に注目しています。個人の身体に大きな影響を伴う臨床研究では、その参加に際して個人から事前に同意を取得するべきであり、またその撤回の希望は最大限尊重されるべきでしょう。しかし、既存の試料やデータを用いる研究は、個人に及ぼす害の防止や軽減、研究者や倫理審査委員会の責任ある判断を前提として、多様な参加・収集形態があっていいと考えてます。影響力が大きい文書ですので、用語の詳細な定義や解説の充実などが期待されます。
なお、井上が滞在しているウプサラ大学研究倫理・生命倫理センターのウェブサイト(9月22日記事)、週刊ブログ(9月25日記事)でもこの短報が紹介されています。
(井上:ウプサラ大学にて在外研究中/スウェーデン王国)
雑誌「医学のあゆみ」で「臨床研究と倫理」という特集が組まれました(国立循環器病研究センター・松井健志氏の企画、詳しくはこちら)。本教室の丸、井上が、それぞれ「臨床研究におけるインフォームドコンセントと”治療との誤解”」「ヒト試料の取扱いと研究倫理」という単元を担当しています。
「インフォームドコンセント」(丸)の単元では、「研究目的での侵襲」に関するインフォームドコンセントが果たす役割と注意点を紹介しました。被験者からの同意の取得は、研究倫理における基本的な要件ですが、単に同意を得たという事実や被験者が同意したとおりに研究を展開するというだけでは、被験者保護として十分ではありません。研究による侵襲が正当化されるためには、研究に伴う危険やリスクに照らして、科学性・倫理性を担保するための倫理委員会における評価の充足や被験者との必要なコミュニケーションのあり方を考える必要があります。また、研究の趣旨とは異なる被験者の期待やニーズが、患者・医師関係の中で「治療との誤解」を形成し、結果的に被験者の自律的判断を歪める危険性もあります。狭義の「同意取得」のみならず、被験者が研究参加によってもたらされる(もたらしうる)利益の性格や危険性について理解できているか、研究者は注意する必要があるでしょう。
「ヒト試料」(井上)の単元は、研究目的での試料の取扱いをめぐる問題をテーマとしています。既存の試料を用いる研究では、医薬品の臨床試験などと異なり、個人の身体に直接的な害が生じることは少ないといえます。一方、医療への還元には長い年月を要する場合が多く、健常者・非罹患者の協力を求めることが多いこと、解析結果は大きな集団レベルで示されることなどの特徴があり、また試料は研究の素材として共有、蓄積されたりすることも多いです。個々人と研究結果との関係は相対的に希薄で、試料の提供や維持は、研究方針に包括的に共鳴した人の支持に依拠することになります。解析技術が進歩し、当初想定していなかった用途や情報の発生への対応が求められる中、試料や情報の個人性への配慮と科学研究の素材としての運用との均衡をめぐる議論が浮上しています。前半ではこうした特徴の概要を、後半では試料の取扱いをめぐる自律と無危害をめぐる議論に関連の深い、直近の論点を紹介しました。
第36回(2013年9月20日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
神里:
European Society of Human Reproduction and Embryology
The prevention of hereditary breast and ovarian cancer by PGD is ‘feasible’, following analysis of Europe's biggest patient series
中田:
End-stage heart disease, high-risk research, and competence to consent: the case of the AbioCor artificial heart
E. Haavi Morreim
Perspectives in Biology and Medicine. 49(1):pp.19-34, 2006
岩本:
自殺のない社会へ―経済学・政治学からのエビデンスに基づくアプローチ
第1章 なぜ自殺対策が必要なのか?
澤田康幸、上田路子、松林哲也
有斐閣 2013年06月
本日は以下の報告がありました。
中田(礒部代読):進捗報告
小林:修士論文執筆状況
江:進捗報告、現在の関心
岩本:研究計画案
第35回(2013年9月6日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
會澤久仁子:
Research Ethics Consultation:A casebook
Danis et al.
NY:OUP.2012:69-72
神里:
わが国における研究不正 公開情報に基づくマクロ分析(1)
松澤孝明
情報管理 56(3), 156-165, doi: 10.1241/johokanri.56.156
丸:
Ethical implications of including children in a large biobank for genetic-epidemiologic research: a qualitative study of public opinion
Kaufman D, Geller G, Leroy L, Murphy J, Scott J, Hudson K
AJMG Volume 148C, Issue 1, pages 31–39, 15 February 2008
小林:
企業観の変遷と企業の社会貢献
岩田龍子
日本福祉大学経済論集 特別号(2004.10)
岩本:
ブレインバンクをめぐる倫理的・法的・社会的問題
佐藤雄一郎
脳と精神の医学:第20巻・第1号(2009)
本日、2013年度、第4回目の公共政策セミナーが開かれました。詳細は、以下の通りです。
| 日時: | 9月4日(水)10時~12時 |
|---|---|
| 報告者: | 吉田幸恵(公共政策研究分野特任研究員) |
| タイトル: | 「朝鮮のハンセン病政策再考(仮)」 |
概要:
わたしは近代の朝鮮/韓国のハンセン病政策について調査しています。日本統治下にあった朝鮮では、日本と同じようなハンセン病(らい病)対策がとられていました。
その管理下のもと、朝鮮のハンセン病者たちは「ハンセン病である」ということと「朝鮮人である」ということ、「二重の差別」の中で生を紡いでいました。
1945年以降、日本の管理下から離れ、韓国となったこの国のハンセン病政策はあまり実態があまりわからなくなってしまいました。
日本統治下では日本語での文献が残されてはいるものの、45年以降は当然韓国語文献しかなく、しかもアーカイブ化も進んでおらず「韓国でのハンセン病政策はそれはそれはひどいものだ」という若干恣意的な資料が、日本での「韓国のハンセン病評価」に直結してしまっている現実があります。
実際そうなのか/どうだったのか。このあたりの話を今回は紹介したいと思っています。
The Relationship between Media Consumption and Health-Related Anxieties after the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster (武藤)
2013/08/20
2011年6~7月に、福島県相馬市・南相馬市の放射線量の異なる地区の12か所で、南相馬市立総合病院の坪倉正治医師が放射能と健康に関する説明会を実施していました。その説明会参加者に対して、説明会の前後に協力していただいた質問紙調査のデータをまとめたものが、ようやくPlos Oneに掲載されました! 以下のURLで全文読んでいただけます(英語)。
論文に仕上げた立役者は、当時、国際保健学専攻修士課程に在籍していた杉本亜美奈さん、野村周平さん、助教のスチュアート・ギルモアさんです。当時、メディカルゲノム専攻修士課程の大学院生だった佐藤未来子さんと私は、調査票の設計、データの集計作業等に関わりました。
この論文の前身となる基本集計については、科学技術社会論学会第10回年次研究大会(京都大学)にて、佐藤未来子、武藤香織「浜通りにおける放射線説明会の意義と課題」として報告を行いました。
この報告では、
(1)説明会前後に参加者に質問紙を行ったところ、説明会後は軒並み不安軽減につながっていたこと
(2)説明会で提供しなかった情報以外にも市民の不安軽減に寄与する副次的な効果をもっていたことと
(3)不安軽減の効果は不安の種類に応じて異なっていたこと
(4)報道接触頻度が高い集団で不安度の高かった人の割合は、報道接触頻度の低い集団に比べて15%高かったこと
等を報告しました。
さらに詳しく分析したこの論文では、因子分析によって不安の種類を3つに分類し(放射能による健康への不安、将来の生活への不安、社会生活破たん(social disruption)への不安)、日ごろ接触する情報源(メディア)の種類による不安の持ち方の違いを明らかにしました。たとえば、噂を重要な情報源としている人は、放射能の健康不安をより強く持ちやすく、地方紙を読む人は全国紙を読む人に比べ、将来の生活への不安がより強い、ラジオを聴く人は社会生活破たんへの不安がより強い、といった関連です。
もっとも、このデータの限界としては、調査票が放射能と健康講演会に拘束されるために生じる外的信頼性の問題、SNSについては聞いてないこと、長期的な追跡はできていないこと、女性と高齢者が多いというバイアス等、いろいろとあります。
しかし、東日本大震災から3か月後、事故の影響や規模が未知数の段階で獲得した貴重なデータです。この時期の住民の不安の声を集めたデータは存在しないのではないかと思います。今後、リスク・コミュニケーションやメディア研究の専門家らとも連携して考察を深めることによって、このデータの意味が深められるとともに、今後の同様の事故におけるメディア対応の一助になればと思う次第です。
猛暑お見舞い申し上げます。D2の中田はる佳です。
大変な猛暑が続く中、夏を元気に乗り切ろう!ということで研究員の方のご提案により、研究室のメンバーみんなで鰻を食べに行ってきました。くしくもその日は土用の丑の日の前日で、鰻を食すにはもってこいの日。鰻は大好きなのですが、土用の丑の日についてきちんと知らなかったので調べてみました。
「土用の丑の日(どようのうしのひ)は、土用の間のうち十二支が丑の日である。夏の土用の丑の日のことを言うことが多い。夏の土用には丑の日が年に1日か2日(平均1.57日)あり、2日ある場合はそれぞれ一の丑・二の丑という。」 (Wikipediaより)
まず、土用の丑の日が2日ある場合があることを初めて知りました。今年は7月22日と8月5日だったとのこと(2回鰻が食べられますね)。そして「土用」がわからなかったのでさらに検索。
「土用(どよう)とは、五行に由来する暦の雑節である。1年のうち不連続な4つの期間で、四立(立夏・立秋・立冬・立春)の直前約18日間ずつである。俗には、夏の土用(立秋直前)を指すことが多く、夏の土用の丑の日には鰻を食べる習慣がある。」(Wikipediaより)
暦の数え方ということでしょうか。
由来については深入りせずにこの程度にして、肝心の鰻はというと、かの有名な「野田岩」に行ってまいりました!なんとこの日の前夜に、NHKの番組で野田岩が特集されていて、予習もばっちり。とても重厚なお店のつくりで、歴史が感じられました。私は、うな重とうまきを注文し、野田岩が薦めるワインとの合わせを楽しみました。鰻には日本酒だと思っていましたが、ワインとの相性もよかったです。
おいしいものでエネルギーチャージをして、みんなでざっくばらんに話をし、とても楽しい時間を過ごしました。
写真左:神々しいうまき。冷めないように保温性のあるお重に入って運ばれてきました。
写真右:美しいうな重。山椒もとても薫り高く、おいしかったです。
(D2・中田はる佳)
第34回(2013年8月2日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
丸:
第十三章 プリコミットメントから見たアドバンス・ディレクティブ
丸 祐一
「法」における「主体」の問題 仲正昌樹編 御茶の水書房 2013年7月1日
楠瀬:
Electronic Informed Consent: Possibilities, Benefits, and Challenges
Rahlyn Gossen
Rebarinteractive April 2, 2012
中田:
Informed consent documentation for total artificial heart technology
Katrina A. Bramstedt
Journal of Artificial Organs (2001) 4:273-277
岩本:
自殺対策の推進における家族員の責務とその上昇をめぐって
藤原信行
「現代思想」2013年5月号 特集:自殺論
江:
補完代替医療の選択とSense of Coherence
本江朝美,高橋ゆかり,副島和彦,田中晶子,伊藤マモル
昭和医学会雑誌 Vol.71 (2011) No.4 P 398-407
本日は以下の報告がありました。
岩本:修論研究計画案
中田:進捗報告、学会抄録案
小林:修論中間発表の報告
趙:学会抄録案
江:進捗報告、今後の研究方針
洪、楠瀬:教室内学会発表・論文投稿等に関するルール案
こんにちは!M2の小林智穂子です。
先日(7/3)、学際情報学府修士論文の中間発表会があり、現在の研究進捗状況を発表してきました!
私の研究テーマは、『企業ボランティアの成り立ちと行方』です。研究の目的は、企業活動におけるボランティア活動の位置付けの変遷を明らかにすること。中間発表では、ボランティアと企業活動の接点に係る文献調査の経過報告を行いました。
中間発表の前週、公共政策研究分野の定例ゼミで発表予行をする機会がありましたが、ここで発表の内容や方法についてのコメントをたくさんいただきました。そこから、先生との面談やゼミで受けた質問・コメントのメモ、修論進捗報告をした際に用意していた資料、収集した資料のリストをもとに、これまでのことを振り返りながら、発表資料を一から組み立て直すつもりで手直ししました。そして、本当にギリギリのタイミングで、新たに「結論の一部」を書くことができました。
私は社会人を経て大学院に入学しました。非常勤ですがNPOでも働いています。社会人を経てから大学院に入ると、「解決したい問題」や「晴らしたいルサンチマン」がものすごく具体的なのです。ですから、単なるワタクシ論や経験論にならずに、ちゃんと「研究」になっているのか、というのは、今でも私がもっている最大の課題ですし、いつも不安を感じています。でも、この中間発表を終えて…大げさだけど言っちゃいますと、はじめて「この“研究”は私のもんだ」という感覚を感じることができました。先生や先輩諸氏のご指導なくしては、ここまでやってこられなかった…。いくら感謝しても足りません。
発表後は、安堵やら疲れやら何やらで一瞬放心状態でしたが、ここで新たな課題です。
審査をしてくださった先生がたには、(指導教官以外には口頭で経過報告をするのは初めてだったのですが)「文献だけじゃなく、インタビュー調査などもしては?」と。「せっかく経験もあるのだから。ドロドロとした現実と、理論との間をつなぐのも研究者の仕事だよ。」とアドバイスいただきました。
生々しい現場からアカデミックな世界へやってきて、いったん脇に置いた「なま」の世界に、今度は研究者として入っていく。その訓練をこれから始めます。怖いようなワクワクするような。修論を仕上げるために残された時間はあと半年もありません。ゼミにはフィールドワークやインタビュー調査のプロがたくさん。鍛えてもらおう。日々邁進!です。
わたしの子ども達はもうすぐ夏休み。私は…!?
先生からは、「まだ暑い日が続くなか、汗を拭きふき修論を執筆しているイメージをもとう。コートを着るような時期に描き始めるのでは遅いよ。」と執筆スケジュールに関して、具体的なイメージ付きのアドバイスをいただきました(これ、発表会後の打ち上げで同級生たちにシェアしたところ、「そのイメージ法(?)いいっすねぇ!」と大好評)。これから汗を拭き拭き、執筆を進めたいと思います。
(M2 小林智穂子)
本日、2013年度、第3回目の公共政策セミナーが開かれました。
詳細は、以下の通りです。
| 日時: | 7月10日(水)10時~12時 |
|---|---|
| 報告者: | 趙斌(新領域創成科学研究科 メディカルゲノム専攻 修士2年) |
| タイトル: | 中国における「優生政策」と生命科学政策の相互作用 |
概要:
1980年代に開始された中国の「人口管理・優生政策」と、科学技術政策の間の相互作用について検証するとともに、今後の生命科学技術発展によって母子保健政策におけるゲノム科学の利用がいかなる方向に進むのか、また国際社会との関係性などを検討していく。それから、実際に中国での遺伝相談の医師に遺伝カウンセリングに関するインタビューを計画している。可能であれば、NIPTや胎児WGS研究・実施している中国の会社・病院へのインタビューも検討している。
第33回(2013年7月5日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
佐藤弘之:
What's missing? Discussing stem cell translational research in educational information on stem cell “Tourism”
Zubin Master, Amy Zarzeczny, Christen Rachul, Timothy Caulfield
Journal of law, medicine and ethics
武藤:
Medical research: cell division
Meredith Wadman
Nature 498, 422-426 (27 June 2013)
神里:
Cloning debate: Stem-cell researchers must stay engaged
Martin Pera, Alan Trounson
Nature vol.498, 13 June 2013
What's human? What's animal? And what of the biology in between?
Nik Brown
The Guardian, 25 July 2011
礒部:
統合的参加型テクノロジーアセスメント手法の提案:再生医療に関する熟議キャラバン2010を題材にして
山内保典
Communication-Design. 4. 1-28, 2011
楠瀬:
Therapeutic hope, spiritual distress, and the problem of stem cell tourism
Insoo Hyun
Cell Stem Cell 12, May 2, 2013
International Society for Stem Cell Research 11th Annual Meeting
中田:
Pay-to-participate funding schemes in human cell and tissue clinical studies
Douglas Sipp
Regenerative Medicine. 2012; 7 (6 Suppl): 105-11
趙:
Current genetic counseling in China
Yuan-zhi ZHANG, Nanbert ZHONG
Journal of Peking University (Health Sciences) Vol. 38 No.1 Feb. 2006
岩本:
Advancing Neuroregenerative Medicine: a Call for Expanded Collaboration Between Scientists and Ethicists
Jocelyn Grunwell, Judy Illes, Katrina Karkazis
Neuroethics April 2009, Vol 2, Issue 1, pp13-20
Scientists form new nerve cells-directly in the brain
Science Daily Mar.26, 2013
江:
再生医療とクローン・テクノロジーの衝撃とそれに応じる制度
(中)再生醫學與複製科技之衝擊與制度回應
范建得、何建志
法律與生命科學 第七期
2008年10月
はじめまして、研究員の礒部です。
今後、つれづれなるままに、報告などを書いていければと思います。よろしくお願いします。
今回は学会参加&発表報告です。
2013年6/20~6/23に京都国際会館で開催された、ニューロ2013に参加してきました。学会の詳細については、ブログ「院生室より」の岩本さんの記事をご参照ください。私からは、ポスター発表を行った内容について簡単に報告させていただきます。
私のポスター発表は、6/22の午後の時間帯にありました。発表は以下の共著者、発表タイトルで行いました。
熟議型ワークショップの試行:一般市民はBMIについてどのような論点を有しているのか(A Deliberative Workshop Trial: What Are the General Public's Concerns About BMI?)
礒部太一、水島希、加瀬郁子、大津奈都子、内田麻理香、佐倉統
具体的な発表内容は、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)という脳神経科学の中で萌芽的技術である分野について、一般市民の方々がリスクやベネフィットについてどのような認識を有しているのかを、論点抽出ワークショップを実施することで明らかにすることを目的としたものです。
ニューロ2013は、神経科学系の学会のため、私達の発表のような脳神経科学の倫理的・社会的を扱ったものは数少なかったのですが、多くの聴衆の方々が質問に来てくださり、有意義な発表の機会となりました。今回の学会は京都で開催されましたが、次回は横浜での開催が予定されています。次回も継続して発表を行い、神経科学系の学会の中での倫理的・社会的問題の捕捉や解決について少しでも貢献できればと思います。
2013年7月より、特任研究員として、高嶋佳代さん・楠瀬まゆみさん(前職:学術支援専門職員)をお迎えしました。
どうぞよろしくお願い申し上げます!
本日は以下の報告がありました。
小林:修士論文中間発表の予行
中田:文献調査の進捗、学会参加報告(米国人工臓器学会)
岩本:研究テーマの紹介、学会参加報告(科学基礎論学会、Neuro2013)
趙:ポスター発表のふり返り、来月の公共政策セミナーの準備状況
院生室(通称3研)には、様々な研究テーマを持った院生が集っています。研究をよりよいものにするには、いろんな人の意見をもらいながら進めていくことが重要です。公共政策研究分野には、院生が研究発表をしたり研究相談をできるミーティングがいくつか用意されています。今日は、それぞれのミーティングで院生がどんなことをしているかをご紹介します。
◆公共政策セミナー(月1回)
原則として毎回一人の担当者が、自身の研究進捗や論文構想の発表を行います。院生にも年1回担当が回ってきます。このセミナーでは、学会等での発表に準ずるレベルでの報告が求められ、自身の研究全体に対するコメントをもらうことができます。ここで参加者から出されたコメントへの対応が、学会発表のときに活かされることもあります。また、発表しない回でも他のメンバーの研究を理解し、それへのコメントを出すことが求められます。これは、学会等で質問をする練習にもなります。
◆ジャーナルクラブ(月2回)
自分の興味がある文献を各自が持ち寄って、一人5分程度で内容を紹介します。文献の種類は問わず、内容も自由です。院生は原則毎回文献を紹介することになっています。ジャーナルクラブに毎回参加することで、文献の要点を理解し、まとめる力が蓄積されていきます。また、自身の研究テーマに沿った文献をまとめる作業を定期的にすることで、自分に足りない情報がわかり、今後読むべき文献のめどが立てられます。さらに、他のメンバーの文献紹介を聞くことで、知らない分野の情報を得ることができます。
◆[New!!] 定例ゼミ(月2回)
研究員の方々のご提案により、今月から新しく「定例ゼミ」が発足しました。このゼミは、細かな研究進捗状況の報告や研究相談、また、学会参加報告などメンバーで情報共有をする機会として設けられました。院生は最低月に1回は報告することになっています。学会発表や学位審査の発表の予行などをさせてもらうこともできます。日々の研究でちょっと困ったことなどをメンバーに相談することができる機会になると思います。
※初回は、M2の小林さんが修論中間発表の予行を行いました(写真)。参加したメンバーからは様々なコメントやアドバイスが出されていました。
こうした研究室内のミーティングは、院生にとって、研究のブラッシュアップとともに学外発表の練習・他分野の研究者との議論の練習によい機会となっています。
(D2・中田はる佳)
はじめまして。修士課程一年の岩本八束です。不安定な天気が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
6月15・16日は科学基礎論学会(大阪)に、21-23日はNeuro2013(京都)に参加してきました。二週連続で新幹線での遠出がありましたが、得るものも多くありました。
科学基礎論学会は主に科学哲学者や科学者が集まる学会で、講演やシンポジウムも科学哲学系のものでした。余談ですが、これが人生初学会で、大阪初訪問。今年は物理学の哲学や心の哲学に関する報告が多く、例年に比べて生物学や医学系の報告は少なかったそうです。学部時代は生命科学が専門で、現在も科学哲学は専門とはしていないため、理解が及ばない話もありましたが、大変興味深い話題ばかりでした。特に興味深かったのは、今話題(?)のDSM-5(精神障害の診断と統計の手引きの第五版)に関するワークショップでした。これを機に、精神疾患の診断に大きな変化が訪れる…と思います。
国立京都国際会館で行われたNeuro2013とは日本神経科学学会、日本神経化学会、日本神経回路学会の脳科学関連3学会の合同大会です。神経の文字が多数名を連ねていますが、内容ももちろん脳神経科学づくしでした。こちらの学会は英語でのセッションが多くを占めており、最初は不安でしたが次第に慣れることができました。ランチョンセミナーや教育講演、海外の著名な研究者のプレナリーレクチャーが開かれたりと、非常に充実したプログラムが組まれていました。神経新生に関する話や、エピゲノムの話など、まだまだ脳神経にはわからないことだらけで大変面白いと改めて実感しました。アメリカではヒトゲノム規模で脳の解明を目的としたプロジェクトを立ち上げているそうです。
さて、その脳神経科学が応用・発展されていくにはトランスレーショナルリサーチ(基礎研究から臨床応用へと結びつける研究)を促進したり、ブレインバンク(大規模な脳の集積活動、またはその団体)を整える必要が出てくるでしょう。Neuro2013ではそのようなセッションも用意されており、研究している方等の意見も多数聞くことができました。これからは患者(被験者)・臨床医・(基礎)研究者の三者で手を取り合いながら医療を発展させていく時代が来るだろうと仰る方もいました。また、運が良いことにブレインバンク関係者と長い時間お話させていただける機会も得られました。
空いた時間には観光もできたのでリフレッシュともなりました。渉成園の睡蓮が綺麗でした。鴨もおいしs…かわいかったです。
前述したとおり、今回初めて学会に参加したのですが、大変実りのあるものとなりました。知識も増えますが、意欲も湧きます。次回は発表を見る側では無く、発表をする側に回れたら、と思います。
(M1 岩本八束)
第32回(2013年6月21日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
中田:
High-profile research & the media. The case of the AbioCor artificial heart.
E. Haavi Morreim
Hastings Center Report. 2004 Jan-Feb;34(1):11-24.
趙:
我国遗传服务和出生缺陷干预相关问题探讨
(Issues of Genetic Services and Birth Defects Intervention)
睢素利(SUI Su-li)
Chinese Medical Ethics. Apr. 2013 Vol. 26 No. 2