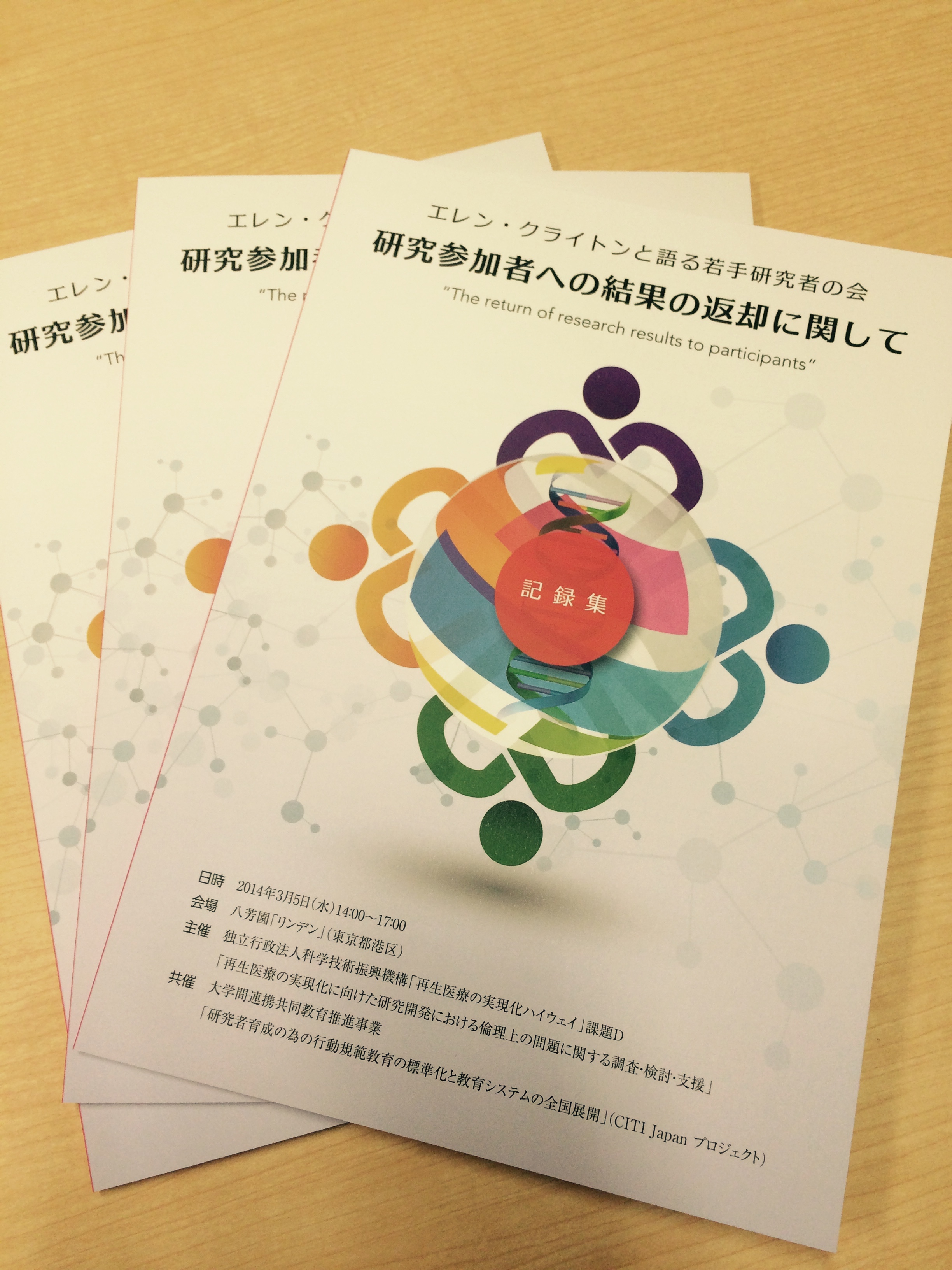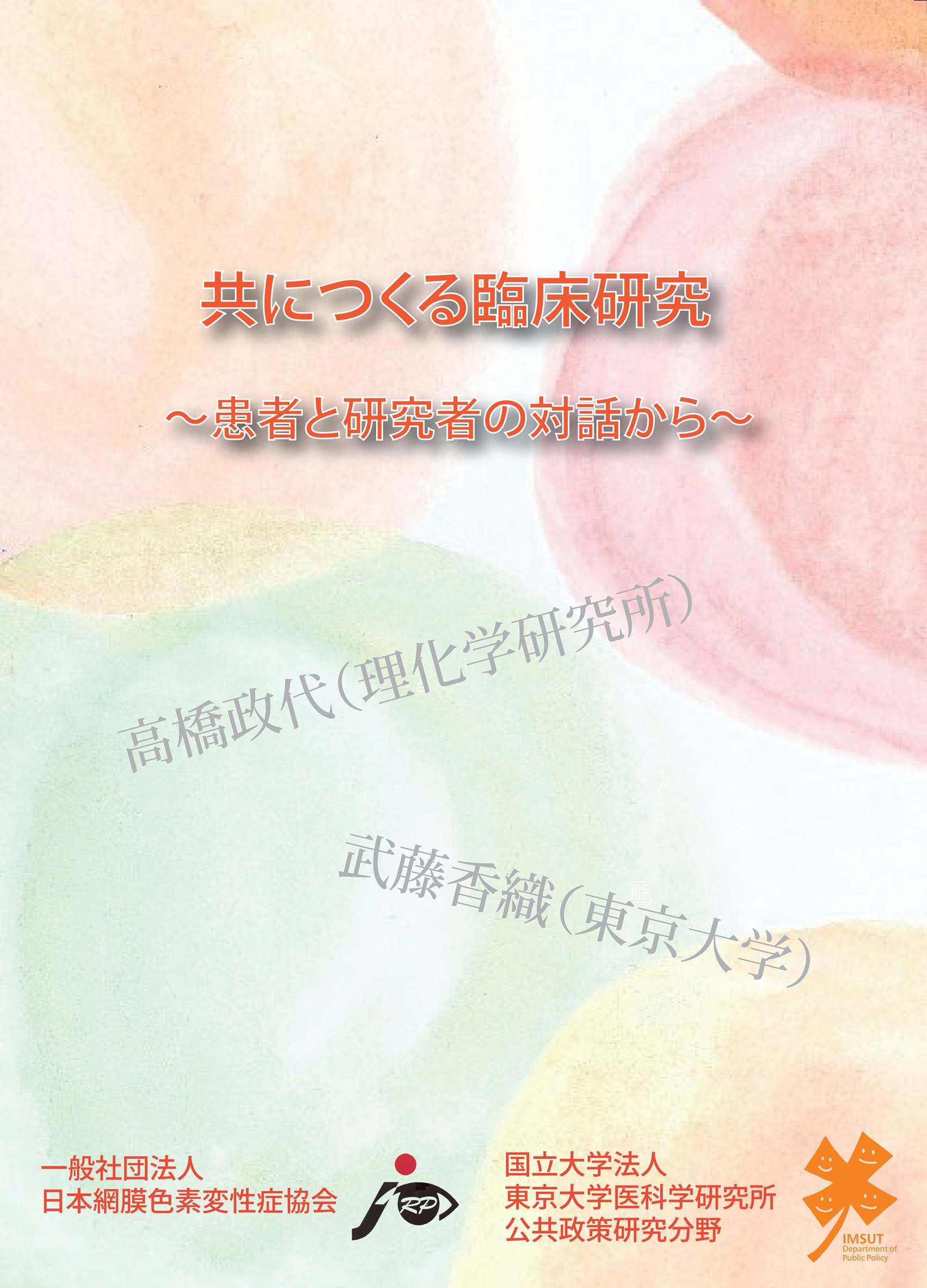先日の大阪での勉強会は盛況のうちに終了いたしました。
お天気に恵まれた三連休の初日にも関わらず、多くの方にご出席いただきました。中には「さっき看板を見たので」とショッピングの途中で参加してくださった方もいらっしゃいました。
氏原さん、中田の2名がお話しいたしましたが、皆さん大変熱心に耳を傾けてくださり、質問やご意見もたくさん出て活発な会になったと思います。私たちのプロジェクトを一般の方に直接ご紹介するのは初めてでしたが、いろいろな感想をいただき、こちらとしても大変有意義な時間でした。
ご参加の皆さまには心よりお礼申し上げます。
また、これからも本プロジェクトへのご関心をお寄せいただければ幸いです。
(2015.1.13追記)
皆様、はじめまして。
本プロジェクトでインタビューを担当しております、大学院生の中田はる佳です。
このたび、臨床試験・治験と私たちのプロジェクトについて、皆さんと一緒に考える機会を持ちたいと考え、勉強会「臨床試験・治験について語り合おう~体験談の共有に向けて~」を開催することにいたしました。
「そもそも、臨床試験・治験ってなに?」「なぜ、体験談を集めようとしているの?」「体験談を集めて、どんな役に立つの?」などなど、皆さんが感じる疑問に答えると同時に、私たちも皆さんがどんなことに疑問をお持ちなのか勉強させていただきたいと思っています。
そして、今回は国立病院機構大阪医療センターなどのご協力を得て、関西エリア(大阪)で開催いたします。大阪なら行けるという方、ぜひお越しください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
お申込み、お問合せはこちらから。
毎日新聞 2014年12月22日 地方版にこの勉強会の案内を掲載していただきました!
「勉強会:新薬開発の臨床試験・治験とは 来月10日、大阪・北区で /大阪」<12月24日追記>
[文責:中田]
D3の中田はる佳です。
これまで博士論文の審査過程を何回か書いてきましたが、今回は「博士論文本審査会」についてご紹介します。
指導教員や研究室メンバーの皆様から多大なご指導をいただきながら、昨年の12月上旬に博士論文を提出しました(柏キャンパスまで持参します)。その後、審査委員の先生方に論文をお渡しにいき、(おそらく年末年始のお休みに)読んでいただきました。
博士論文本審査会は、主査・副査の先生方にお集まりいただき、非公開で行われます。30分程度のプレゼンを準備していき、途中で適宜質疑応答をはさむという流れで進みました。研究科によっては、プレゼン時間が厳密に定められているところもあるようです。プレゼンと質疑応答で1時間半ほど審査員の先生方とやり取りをし、その後いったん退室して審議をしていただきました。審議後、指導教員から必要な修正などを教えていただきます。
これで一通りの審査は終了です。あとは期日までに最終合格を得られるか、というところです。
(D3・中田はる佳)
第55回(2014年12月19日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
岩本:
Biobanking 3.0: Evidence based and customer focused biobanking
Daniel Simeon-Dubach and Peter Watson
Clinical Biochemistry. 47:300-308. 2014
江:
Survey of genetic counselors and clinical geneticists' use and attitudes toward pharmacogenetic testing.
SB Haga, JM O'Daniel, GM Tindall, R Mills, IM Lipkus and R Agans
Clinical genetics. 82(2):115-120. 2012
李:
「子どもを対象者とする研究の倫理:序論―研究規制の成立背景と倫理的ディレンマ」
栗原千絵子
『臨床評価』34(1): 103-122.2007
藤澤:
『連帯の挨拶――ローティと希望の思想』「第3章 アイロニーと連帯による「正義」――ローティのリベラリズムを読み抜く」
安部彰
生活書院 2011
M2の岩本八束です。読書の秋があっという間に過ぎ去り、こたつと蜜柑が欠かせない季節になりました。
先日、2014年の忘年会が開かれました。上半期納会同様、高い出席率となり、まさに「忘年」にふさわしい会となりました。今回の忘年会では、余興として句会が開催されました。句会は「本」あるいは「みかん」をお題に、事前に俳句あるいは川柳を無記名で詠み、忘年会当日に投票、という形式で行われました。見事一位に輝いた方には武藤先生から素敵な景品が授与されました。個性的で味わい深い句が集まり、大変楽しい会となりました。
2014年も残りわずか。寒い日が続きますが、くれぐれもお体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
それでは、良いお年を!
(M2・岩本八束)
本日、2014年度、第9回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:2014年12月12日(金)10時30分~12時30分
| 発表者: | 中田はる佳(新領域創成科学研究科・博士課程3年) |
|---|---|
| タイトル: | 当事者の視点から見た臨床試験・治験における倫理的課題の探索(博士論文審査会予行) |
第54回(2014年12月5日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
武藤:
23andMe Bring CE Marked Parsonal Genome Service® to the UK
23andMe Press Release 2014.12.2
23andMe's Health-related DTC Testing Service Aims for Friendlier Reception from UK Regulators
Turna Ray
Genomeweb Dec 02, 2014
中田:
lack of publicly available scientific evidence on the safety and effectiveness of implanted medical devices
Zuckman D, Brown P, Das A.
JAMA Internal Medicine. 174(11):1781-7. 2014
岩本:
Characterizing biobank organizations in the US: results from a national survey
Gail E Henderson, R Jean Cadigan, Teresa P Edwards, Ian Conlon, Anders G Nelson, James P Evans, Arlene M Davis, Catherine Zimmer and Bryan J Weiner
Genome Medicine. 5:3. 2013
李:
Handling ethical, legal and social issues in birth cohort studies involving genetic research:responses from studies in six countries
Nola. M. Ries, Jane LeGrandeur, Timothy. Caulfied,
BMC Medical Ethics. 11:4. 2010
第53回(2014年11月21日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
武藤:
血液型と性格の無関連性――日本と米国の大規模社会調査を用いた実証的論拠――
縄田 健悟
『心理学研究』85(2):148-156.2014
神里:
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(疫学・臨床研究統合指針)をめぐって(特集 生命倫理・医療倫理の最前線)
位田 隆一
『京都府立医科大学雑誌』123(8):537-544.2014
中田:
Invisible Risks, Emotional Choices — Mammography and Medical Decision Making
Lisa Rosenbaum
The New England Journal of Medicine. 371(16):1549-52.2014
岩本:
What is a biobank? Differing definitions among biobank stakeholders
D.M. Shaw, B.S. Elger and F. Colledge
Clinical Genetics. 85(3):223-7.2014
本日、2014年度、第8回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:2014年11月14日(金)13時~15時
| 発表者: | 李 怡然(学際情報学府・修士課程1年) |
|---|---|
| タイトル: | 「不妊」におけるカウンセリングの多様性―カウンセラーの経験と場に着目して―(日本社会学会大会予行) |
概要:
不妊当事者の抱える心理・社会的な困難が指摘され、医療者・治療経験者とのコミュニケーションを望む声が報告されてきた。日本では2000年代よりカウンセリングの整備が進められてきたが、その具体的な実践の内容にまで踏み込んだ研究の蓄積は少ない。本研究ではカウンセラーへのインタビュー調査を通し、当事者の抱える「葛藤」をどのようにとらえ、支援を行っているかについて明らかにする。本報告では個別の差異に着目し、カウンセリングの現状と今後の不妊当事者への支援の可能性について考察する。
D3の中田はる佳です。
今回は、先日行われた「博士論文予備審査会」についてご紹介します。
これは、3月修了予定の博士の学生を対象に、博士論文の概要と進捗を主査・副査の先生方の前で発表するもので、学位審査プロセスのひとつです。5月に行われた中間報告会では副査の先生方2名にお越しいただきましたが、今回は主査・副査の先生方全員にご報告をしました。審査会は、学生一人15分(発表10分・質疑応答5分)の持ち時間で、白金台と柏を中継して行われます。審査会に先立って、学生はA4用紙4枚の要旨を提出しており、当日はそれが要旨集としてフロアにいる人に配られます(予備審査会場には、発表者・審査員以外でも名簿に名前を書けば入れるようで、私も去年見学に行きました)。
10分という限られた時間で、発表形式は研究室によって様々で、実験結果と考察を中心に発表している学生もいましたが、私は研究全体の概観がわかるような形式にしました。質疑応答の時間には、主査・副査の先生方はもちろん、フロアにいらっしゃる他の先生方からも質問をいただきました。論文には、いただいた質問やコメントに応える内容を書き込んでいきたいと思います。学会発表と異なり、論文完成までに残されている課題を明示して、進捗がわかるようにしておくことも重要なポイントだと思いました。
短い時間で自分の研究を伝えるには、自分が考える最も大事なところ・相手に伝えたいところを明確に意識しておかなければなりません。研究の要点を集約する力、それを伝える力は普段参加しているジャーナルクラブやセミナーなどを通じて蓄積されているのだろうと感じました。
時が過ぎるのは早いもので、次のステップは、12月上旬の論文提出です。
(D3・中田はる佳)
本日、2014年度、第7回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:2014年11月7日(水)13時~15時
| 発表者: | Jennifer Viberg (PhD student, Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala University, Sweden) |
|---|---|
| タイトル: | Understanding and handling incidental findings in biobank research and genome sequencing studies |
本日、2014年度、第5回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:2014年11月5日(水)10時~12時
| 発表者: | 中田はる佳(新領域創成科学研究科・博士課程3年) |
|---|---|
| タイトル: | 当事者の視点から見た臨床試験・治験における倫理的課題の探索(博士予備審査会予行) |
概要:
臨床試験(治験含む)は新薬や医療機器等の開発に欠かせない。よりよい実施体制の構築には、被験者の考えを反映する必要がある。これまで、臨床試験に関して患者・一般市民の理解促進や情報ニーズ等に関する研究は行われてきているものの、いずれも小規模であった。本研究では、患者の意識・経験を明らかにした上でそこからみえる倫理的課題について検討し、臨床試験に関する政策や規制へのフィードバックを行う。
研究参加者に対して、どのような結果を返却するべきかという問題に関して、研究領域毎に様々な議論がなされています。そこで、2014年3月5日に、CITI Japanプロジェクトの協力により、結果の返却に関して主要な論者の一人であるEllen Clayton氏をお迎えし、日本の若手ELSI研究者との対話型集会を開催いたしました。
この機会に、研究領域毎に閉じた議論をしてきた研究結果の返却をめぐる議論を、一度、「横串」にしてみるというのが、今回のコンセプトでした。Clayton氏の講演の後に、脳科学、ヒトゲノム解析研究、幹細胞治療研究という3つの異なる研究領域における論点を、日本の若手ELSI研究者から提示してもらい、フロアからのディスカッションも大変盛り上がりました。本記録集は、この集会のエッセンスをまとめたものです。
この記録集冊子の入手をご希望の方は、 までお申し込みください。
PDF版はこちらからダウンロードできます。
※この記録集作成にあたり、科学技術振興機構科学技術振興機構「再生医療の実現化ハイウェイ」における、「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究」(課題D)より財政的支援を得ております。ここに御礼申し上げます。
東京大学にはたくさんの「特任」の職員がいます。
国からの委託事業等、研究プロジェクトごとに採用される「特任」には基本的に任期があります。
いわゆる「ポスドク問題」とも密接に関係しているといえばしているのですが、、、かくいう私も特任研究員です。この教室のスタッフはほとんどが「特任」で、様々な研究プロジェクトをおこなっています。
今回、東大新聞で「特任ポスト」について特集が組まれることになり、なぜか弊室の武藤(特任を雇う側)と吉田(特任として雇われる側)に取材依頼が舞い込んできました。
任期のある「特任」は確かに先行きが不安な部分もあります。しかしながら「教職員の終身雇用資格(テニュア)を得れば、それでゴールという考え方は古い」という武藤の意見には大いに共感します。
興味のある方は是非ご覧下さい。
pdfはこちらから。
(文責・吉田)
第52回(2014年10月17日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
岩本:
Newspaper coverage of biobanks
Ubaka Ogbogu, Maeghan Toews, Adam Ollenberger, Pascal Borry, Helene Nobile, Manuela Bergmann, Timothy Caulfield
PeerJ. 2:e500. 2014
江:
“Don't know” Answers, Guessing Effect and Knowledge Levels: The Evidence from Genetics Knowledge Scale
杜素豪 廖培珊
『調査研究―方法與應用』19:67-99 2006
李:
「我が国の母子コホートにおける近年の状況,および母子保健研究から今後への展望」
吉田穂波 加藤則子 横山徹爾
『保健医療科学』63(1):32-38 2014
藤澤:
「第7章 仏語圏の生命倫理」
小出泰士
『シリーズ生命倫理学 第1巻 生命倫理学の基本構図』、今井道夫 森下直貴 責任編集、2012
第51回(2014年10月03日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
神里:
Editorial. German research organizations need to help their workers to defend animal research
Nature 513: 459-460. 2014
中田:
Sham controls in medical device trials
Rita F. Redberg
New England Journal of Medicine. 4;371(10):892-3. 2014
岩本:
Assessing the impact of biobanks
Anne Cambon-Thomsen
Nature Genetics. 34(1):25-6. 2003
李:
「日本の小児医療におけるInformed Assent理念の課題―国連子どもの権利委員会『一般的意見No.7乳幼児の権利』の関係を中心に」
山本智子
『生命倫理』19(1):4-12 2009
藤澤:
「第5章 米国および英語圏のバイオエシックス」「第6章 独語圏の生命倫理」
香川知晶(第5章)、松田純(第6章)
『シリーズ生命倫理学 第1巻 生命倫理学の基本構図』、今井道夫 森下直貴 責任編集、2012
昨今、体質や病気、能力、容姿など、様々な「遺伝子検査」に関する宣伝に触れる機会が増えてきました。しかし、もし購入しようとするときには、いくつか考えて頂きたいことがあります。2012年に、経済産業省から、「こんな検査を受けようとしている貴方に」というパンフレットも出されていますので、ご参照ください。
私は、遺伝子検査による倫理的法的社会的な問題について研究をしてきましたが、このパンフレットとは別の表現で、ぜひ一度、考えて頂きたいと思うこと・10か条を書きます。「購入する」ボタンをクリックする前に、あるいは、医師やエステ等で勧められて「買います!」という前に、セルフチェックしてみてください。
※色々な方のご意見を聞いてバージョンアップしようと思っていますので、ぜひお聞かせ下さい!(10月6日追記)
※Ver.1.1=ご意見を頂き、小見出しをいれました。(10月7日追記)
- 診断ではありません
現在、あなたが直接購入できる遺伝子検査は、現在の体調に関する医師の「診断」とは全く違います。あくまでも将来に関する「確率の情報」であって、あなた自身がその病気に将来かかるか/かからないかは、わかりません。 - 会社によって答えはバラバラです
あなたの遺伝情報の並び順は、一生変わりません。しかし、その遺伝情報と、病気や体質との関わりを示す確率の計算式は、遺伝子検査を販売している企業によって大きく異なり、その計算式は企業秘密となっています。もし複数の会社の遺伝子検査を買ったら、異なる確率の結果が返ってくるでしょう。そのつもりでお付き合いを。 - 研究が進めば、確率は変わります
現在、販売されている遺伝学的検査は、まだまだ研究途上のものも含まれています。研究が進めば進むほど、病気や体質との関わりを示す確率や解釈は、大きく変わっていきます。そのつもりでお付き合いを。 - 予想外の気持ちになるかもしれません
検査結果を読んで、精神的なショックを受けたり、誤解したりしてしまう可能性があります。申し込む前に思っていたのとは違う、予想外の気持ちや感情がわいてくることもあります。 - 知らないでいる権利の存在を知りましょう
だから、遺伝医療の世界では、遺伝学的検査の結果を「知らないでいる権利」という考え方を大切にしてきました。もし仮に購入してしまった後であっても、あなたには、届いた情報を開封しない自由があります。 - 知った後は戻れません
何でもそうですが、知った後は、知らなかった状態には戻れません。でも、まあ、見なかったことにして、棄ててしまうのも自由です! - 自分で知ろうと決めたなら、医師に頼るのはやめましょう
検査結果を読んでも、よくわからなかったときに、安易に医師に頼ろうと思わないでください。あなたが購入した商品(検査)の提携先医療機関以外の、一般の診療所や病院は、この商品のアフターサービスを求める場所ではありません。 - 血縁者と共有している情報を大切に扱いましょう
あなたの遺伝情報はあなたのものでもあるけれども、あなたと生物学的につながりのある人たちとも共有している大切な情報です。だから、遺伝子検査は、血縁者(あなたが思っている人とは違う人かもしれません)にも影響を与える結果を示します。SNSに晒したりするのは、絶対にやめましょう! - 強制検査・無断検査はダメ、プレゼントにも不向きです
気になるからといって、家族、交際相手、友達、上司・部下など、あなた以外の人のDNA(を含む身体物質)を無断で入手したり、他者に遺伝学的検査を受けるよう強制したりしてはいけません。結果を見せるように要求するのもNG。本人が望んでいるかわからないのに、サプライズとしてプレゼントしないほうがよいでしょう。 - 子どもには、大人になって自分で選べる権利を残しましょう
特に未成年者の遺伝情報は、しっかり保護してあげることが成人の務めです。子ども向けの遺伝子検査や、子どもとの血縁関係を調べる鑑定も、日本では販売されています。しかし、そうした検査や鑑定を受けることが、本当にそのお子さんのためになるのかどうか、単に親の興味や都合が理由ではないのか、よーくよーく考えてください。
いわゆる「遺伝子検査ビジネス」の一つである、「DTC遺伝子検査」(消費者に直接販売する遺伝学的検査,Direct-to-consumer genetic testing)を通じたヘルスビッグデータの創出をテーマに、東京大学医科学研究所とDeNAライフサイエンス社との間で共同研究が実施されています。この内容は、クオンタムバイオシステムズ社との新しいシークエンサー開発とともに、革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)のサテライト拠点としての事業とも位置付けられてきました。
私自身は、これまで「遺伝子検査ビジネス」に関する倫理的法的社会的諸問題に関心をもって研究して参りましたが、
- 私自身は、「遺伝子検査ビジネス」を推奨する立場にはありません。
- DeNAライフサイエンス社との間には、一切の「経済的な利益関係」はありません。
- DeNAライフサイエンス社を含め、DTC遺伝子検査企業の倫理委員会の委員は、務めておりません。
しかし、発足当初から、NPO法人個人遺伝情報取扱協議会(CPIGI)の評価委員を務めており、現在、同協議会の「個人遺伝情報を取扱う企業が遵守すべき自主基準」の制定・改正、また現在進めている認定制度の構築も可能な支援をしております。それはいわゆる「遺伝子検査ビジネス」に関して、日本国内で特段の規制がなされる様子がなかったため、まずは業界団体の健全化が急がれると考えたからです。
「DTC遺伝子検査」に対する主な批判の一つに、医師ではない者が「医業」を行い、「診断」に近い検査項目を提供しているではないかという指摘が挙げられます。私自身は、「DTC遺伝子検査」が「医業」に該当するかどうかは、しかるべきステークホルダーが集い、議論されるべきであり、結果として「医業」に該当するとの結論に至ることもあるだろうと考えます。
しかしながら、現在、急速に進展するゲノム医学に関して、専門的な知識やそれらを消費者・患者に現時点で最適な解釈を添えて説明する力を持ち合わせていない医師は、まだまだ多いと考えます。また、「DTC遺伝子検査」を利用して消費者の不安を煽り、高価な診療や精密検査、サプリメントに誘導するような医療機関もあります。そのため、もし「医業」に限定することになったとしても、医療専門職としての自主規制は徹底して行っていただきたいと考えます。単に企業を締め出すだけでは意味がありません。
それ以前の問題として、日本では、「DTC遺伝子検査」のみならず、医療機関が実施する遺伝学的検査についても、その質(正確さ、適切さ、個人情報保護や倫理面への配慮等)を保証する義務を課すような仕組みは存在していません。学術団体や業界団体による自主的な取り組みによって、「あるべき姿を示す」という手法が中心でした(そもそも臨床検査に対して、その質を管理する法律が存在しませんでした)。以下、その一例を紹介します。
これまで様々な団体が、遺伝学的検査の質を担保する努力をしてきたことも事実です。しかし、医療機関・企業を含め、遺伝学的検査を実施する全ての機関において、検査の質の正確さや検査施設の適切さを客観的に評価し、公開する制度の構築が必要だと考えています。
- 日本人類遺伝学会(2010)「一般市民を対象とした遺伝子検査に関する見解」(PDF)
- 特定非営利活動法人JCCLS日本臨床検査標準協議会(2010)「遺伝子関連検査に関する日本版ベストプラクティスガイドライン」
- 日本医学会(2011)「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(PDF)
- 一般社団法人 日本衛生検査所協会(2013)「遺伝子関連検査の質保証体制についての見解」
本日、2014年度、第5回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:2014年10月1日(水)10時~12時
| 報告者: | 岩本八束(新領域創成科学研究科・修士課程2年) |
|---|---|
| タイトル: | メディアにおける「バイオバンク」の語られ方-日米の新聞記事比較を通して |
概要:
現代の生命科学・医学研究において、ヒト試料を用いた研究は不可欠であり、ヒト試料の収集・保管・配布を行う「バイオバンク」は重要な役割を担っているが、その認知度は決して高いとは言えず、社会と「バイオバンク」との関係構築は途上にあると言える。関係構築に当たり、マス・メディア、特に新聞は重要な役割を担うと考えられるものの、これまで新聞記事上で「バイオバンク」がどのように扱われてきたのかは明らかにされていない。以上のような背景から、修士課程では新聞記事上において「バイオバンク」がどのような存在として形作られており、どのような問題として取り上げられてきたかを明らかにするべく、メディア言説分析を用いて、日米の新聞記事を比較・検討を行う。今回のセミナーではその進捗状況を報告する。
| 報告者: | 小林智穂子(学際情報学府・博士課程1年) |
|---|---|
| タイトル: | 従業員参加型社会貢献活動の社会学的研究 |
概要:
セミナーでは、これまでの研究成果と博士課程における研究計画をご報告します。今後の研究の概要は、以下の通りです。企業が自社の従業員のボランティア活動を支援する企業ボランティアプロジェクト(NPO支援を目的としたボランティアプログラム)に着目し、従業員ボランティア本人、および、ステークホルダーの実態調査を行い、現状と課題を抽出する。そのうえで、従業員参加型の社会貢献活動モデルを完成させ、福祉社会・勤労者双方の福祉を実現する条件を考察する。
このたび、日本網膜色素変性症協会(JRPS)とのご縁を頂き、日本で初めてiPS細胞の臨床応用に挑む高橋政代氏(理化学研究所)との対話に立ち会う機会を得ました。
高橋氏は、加齢黄斑変性症を対象とした臨床研究からスタートし、やがて対象を網膜色素変性症(RP)にも拡大し、今から数年後に臨床研究の開始を検討しています。
他方、JRPSの各支部のリーダー向けの研修会を企画する責任を負っていた有松靖温氏は、今からの数年間を、RP患者が臨床研究に備え、研究デザインも工夫するための「猶予期間」であると考え、患者と研究者の直接対話の機会を求めて訪ねてこられました。
そこで、2013年10月30日に開催された、第9回JRPS関東甲信越ブロックリーダー研修会の場を借りて、この対話の機会を実現いたしました。この日の発言録をもとに、読者が追体験できるように再構成したのがこの報告書です。
この報告書冊子の入手をご希望の方は、 までお申し込みください。
PDF版をここからダウンロードしていただくこともできます。
※この報告書作成にあたり、科学技術振興機構科学技術振興機構「再生医療の実現化ハイウェイ」における、「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究」(課題D)より財政的支援を得ております。ここに御礼申し上げます。
M2の岩本八束です。今年も秋刀魚の美味しい季節がやってまいりました。
今月9月25日から27日まで、パシフィコ横浜にて第37回日本神経科学大会が行われました。この大会は神経科学(Neuroscience)の学術大会で、医学系の方のみならず、薬学や生命科学、心理学、情報科学など、様々なバックグラウンドの方が参加し、発表を行っていました。非常に魅力的な大会です。
昨年は発表を聴いて回る側でしたが、今年はポスター発表を行う機会を頂く事ができました。人生で初めての学会発表でもあり、小心者の私は、楽しみでありながらも、不安と緊張を抱えてポスターの前に立っておりました。
自分の予想以上に、沢山の方が足を止めてくださり、様々なご示唆を頂くことができました。新たな視点を得ることができたり、自分の研究の甘さを痛感したりと、非常に有意義な学会発表となりました。また、(まだまだ未熟ではありますが)自分の研究に対して自信を持つこともできました。
今回の発表では、私のスケジュール管理の甘さのため、公共政策の先生方にご迷惑をおかけしてしまいました。今回の発表を、楽しかった、で終わらせること無く、今後の研究へと十分に生かしていきます。
(M2・岩本八束)