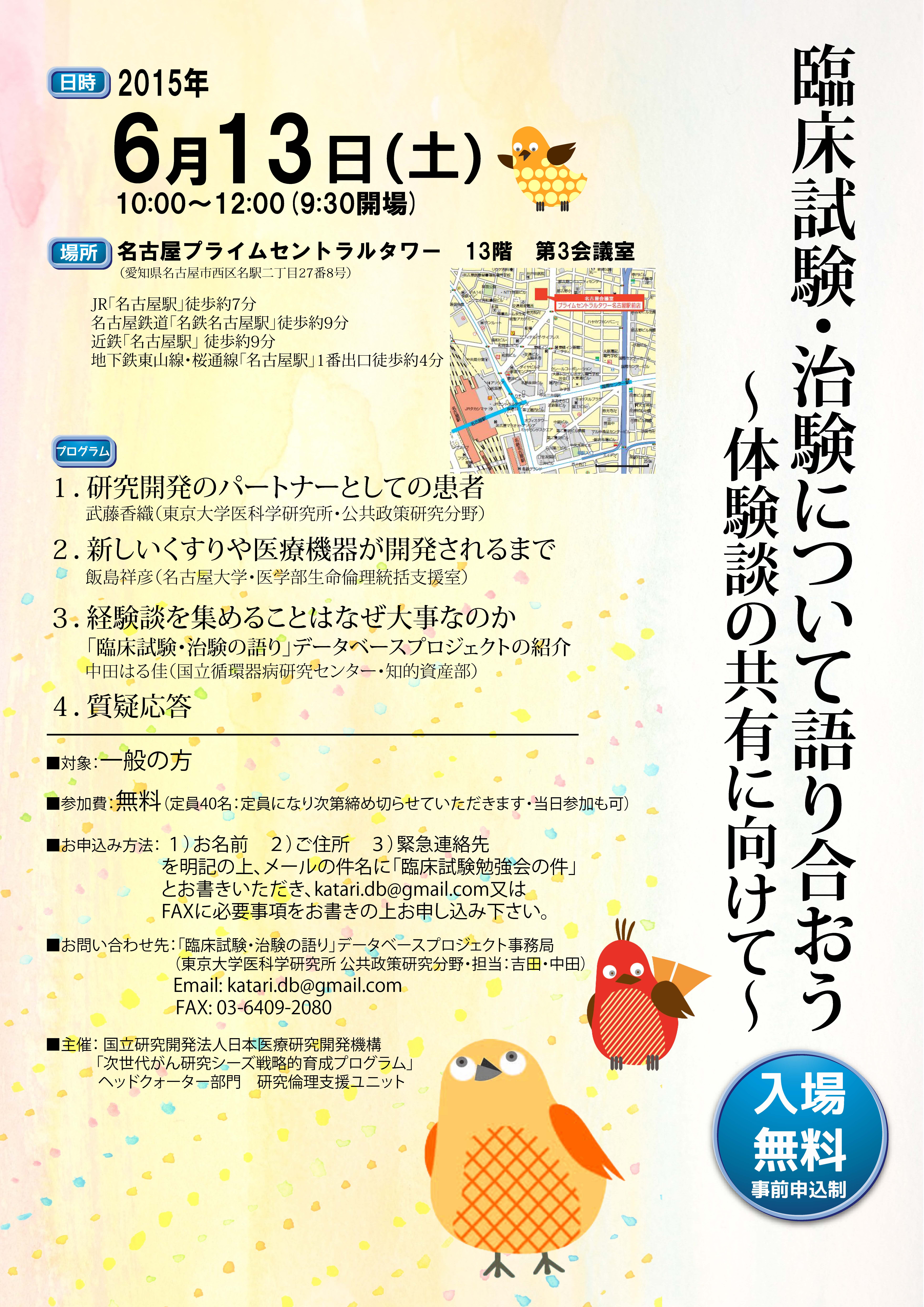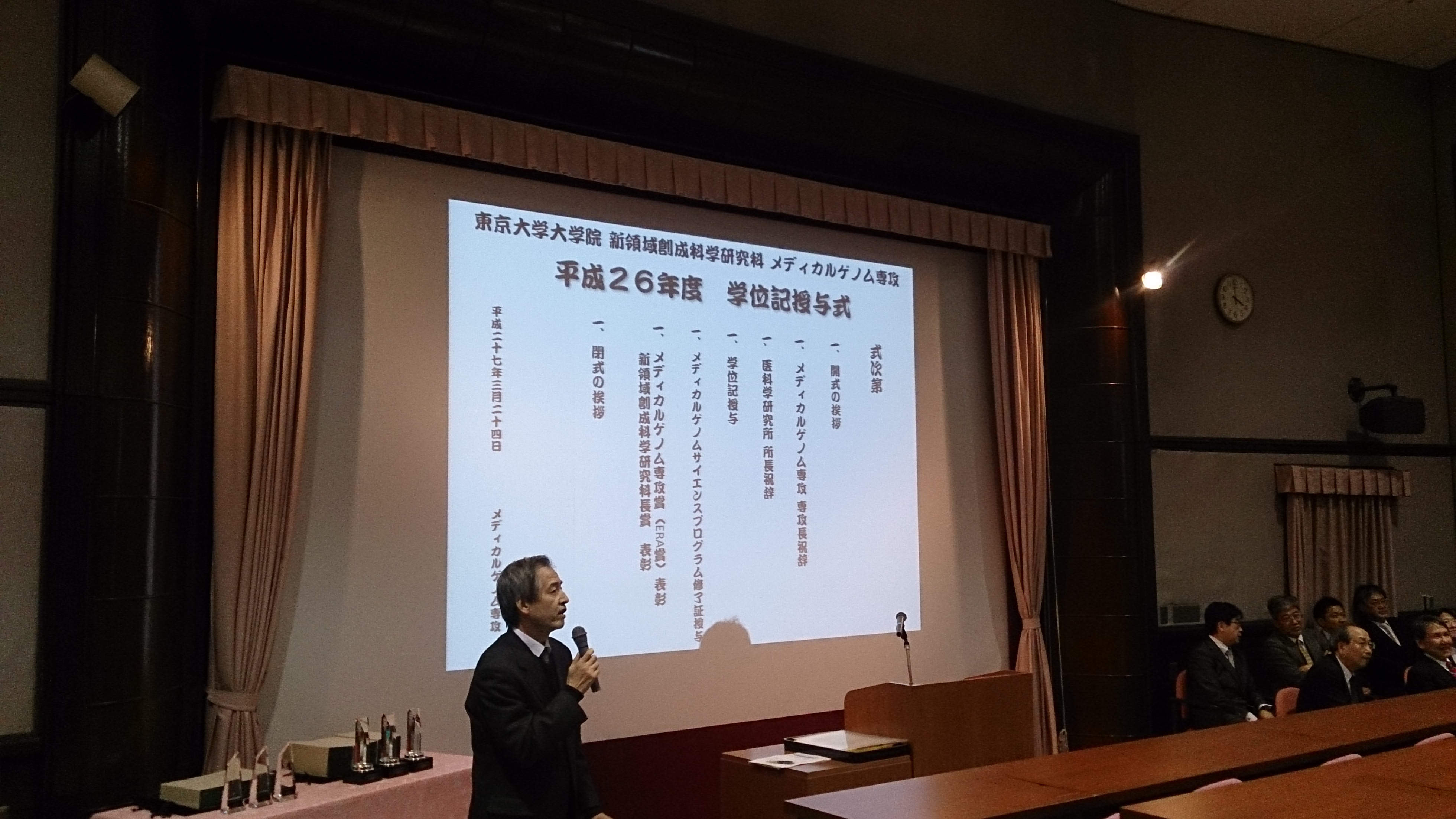梅雨の季節になりました。いつ洗濯すればいいのか悩む季節でもあります。わたしは断固部屋干し反対派です。
こんにちは、特任研究員の吉田です。
多数の皆様にご協力いただいたおかげで、「臨床試験・治験の語り」インタビュー協力者が40名を超えました!本当にありがとうございます。
さて、以前にも大阪・東京と勉強会やシンポジウムを開催してきましたが、三大都市圏のうちひとつだけ回っていない中京圏でも勉強会を開催することになりました。
中京圏の皆様、大変お待たせいたしました!ぜひこの機会に「そもそも、臨床試験・治験ってなに?」「なぜ、体験談を集めようとしているの?」「体験談を集めて、どんな役に立つの?」などなど、皆さんが感じる疑問を教えてください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
お申込み、お問合せはこちらをごらんください。
(文責:吉田)
臨床試験・治験について語り合おう~体験談の共有に向けて~
プログラム:
- 研究開発のパートナーとしての患者
武藤香織(東京大学医科学研究所・公共政策研究分野) - 新しいくすりや医療機器が開発されるまで
飯島祥彦(名古屋大学・医学部生命倫理統括支援室) - 経験談を集めることはなぜ大事なのか~「臨床試験・治験の語り」データベースプロジェクトの紹介
中田はる佳(国立循環器病研究センター・知的資産部) - 質疑応答
| 日時: | 2015年6月13日(土)10:00~12:00(9:30開場) |
|---|---|
| 場所: | 名古屋プライムセントラルタワー 13階 第3会議室 (愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号) JR「名古屋駅」徒歩約7分 名古屋鉄道「名鉄名古屋駅」徒歩約9分 近鉄「名古屋駅」徒歩約9分 地下鉄東山線・桜通線「名古屋駅」1番出口徒歩約4分 |
| 入場: | 無料 |
| 主催: | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」ヘッドクォーター部門 研究倫理支援ユニット |
本日、2015年度、第1回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:2015年5月20日(水)10時00分~12時30分
| 発表者: | 佐藤桃子(学際情報学府 文化・人間情報学コース 修士課程1年) |
|---|---|
| タイトル: | 羊水検査に関する産婦人科医の倫理的判断の変遷 |
概要:
1970年代、優生思想に基づいた羊水検査の実施は「障害者差別である」と社会から批判された。しかし2013年に導入された新型出生前診断(NIPT)など、日本における出生前診断は限定的にせよ存続している。そこで本研究では、出生前診断を実施してきた産婦人科医に焦点を当て、彼らが羊水検査を倫理的にどのように捉えていたかを分析した上で、その倫理観がNIPT導入に及ぼした影響を考察した。本報告では2015年2月に提出した卒業論文の内容を紹介し、今後の展望を述べる。
| 発表者: | 岩本八束(新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 修士課程2年) |
|---|---|
| タイトル: | メディアにおける「バイオバンク」の語られ方―日米の新聞記事比較を通して― |
| 発表者: | 李怡然(学際情報学府 文化・人間情報学コース 修士2年) |
|---|---|
| タイトル: | 医学系研究における子の権利と告知―出生コホート研究を事例に― |
M2の藤澤空見子です。
本日は、武藤研究室活動報告会を開催いたしました!
来年度以降に大学院へ入学し、武藤研究室で研究したいと考えている学生・社会人のみなさまへ向けた研究室説明会として実施しました。
院生生活の紹介だけでなく、学生や研究員の方々による研究成果報告も行い、研究室でどういった研究をしているかを何となくイメージしていただけたかなと思います。
また、他大学の先生や記者の方々をお招きし、研究報告についてのコメントをいただく機会もあり、発表者にとっても有意義な体験になったのではないでしょうか。
報告会終了後は、受験希望の方々と研究室メンバーが交流して、学生生活や研究について様々な話をしていた光景が印象的でした。
写真は、研究成果報告の様子の一部です。
スライド内容の関係で、全体的にぼかしを入れてあります。
少々見づらい写真になってしまい、すみません。
お忙しい中、そして休日の中参加してくださったみなさま、本当にありがとうございました!
第62回(2015年5月15日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
吉田:
ハンセン病疫学と近代日本の地域格差
廣川和花
『歴史評論』746:59-75.2012
佐藤:
Abandoning the dead donor rule? A national survey of public views on death and organ donation
Michael Nair-Collins, Sydney R Green, Angelina R Sutin
Journal of Medical Ethics. 41:297–302.2015
当研究室の活動について広く知って頂くため、下記の要領で活動報告会を開催致します。
【日時】
2015年5月17日(日)午後2時から5時頃まで
【場所】
当研究室<会場アクセス>
【内容】
当研究室所属の大学院生と研究者が日頃の活動や研究内容を紹介し、外部のコメンテーターも交えて意見交換する予定です。当研究室の活動にご関心をお持ちの方、また大学院進学を検討されている方に、お気軽にご参加いただければと思っております。
【お申し込み】
参加をご希望の方は、
までご連絡ください(お名前・所属・連絡先を付してください)。
是非お気軽にどうぞ!
【プログラム(案)】
1.はじめに
2.研究室の紹介
3.活動紹介
- メディアにおける「バイオバンク」の語られ方 ―日米の新聞記事比較を通して―
岩本 八束(東京大学大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻修士課程) - 医学系研究における子の権利と告知 ―出生コホート研究を事例に―
李 怡然(東京大学大学院学際情報学府 文化・人間情報学コース修士課程) - 「家族性」疾患登録の構築 ―研究倫理支援活動を通じて感じた問題点―
高島 響子(特任研究員) - 遺伝子検査販売サービスに対する市民の意識に関する研究
永井 亜貴子(特任研究員)
4.指定発言
増井徹氏(慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター)
三成寿作氏(大阪大学大学院医学系研究科)
5.質疑応答
以上
第61回(2015年5月1日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
高島(響):
Reporting genomic secondary findings: ACMG members weigh in
Scheuner MT, Peredo J, Benkendorf J, Bowdish B, Feldman G, Fleisher L, Mulvihill JJ, Watson M, Herman GE, and Evans J
Genetics in Medicine. 17(1):27-35.2015
岩本:
マス・メディアのAIDSの取り扱いに関する研究―1982年から1992年までの新聞記事の内容分析―
平田繁, 渡邉正樹, 勝野眞吾
『民族衛生』61(1):2-15.1995
李:
‘What Did You Think About That?’ Researching Children's Perceptions of Participation in a Longitudinal Genetic Epidemiological Study
Trudy Goodenough, Emma Williamson, Julie Kent and Richard Ashcroft
CHILDREN & SOCIETY. 17:113–125.2003
佐藤:
Non-invasive prenatal testing: a review of international implementation and challenges
Megan Allyse, Mollie A Minear, Elisa Berson, Shilpa Sridhar, Margaret Rote, Anthony Hung, and Subhashini Chandrasekharan
International Journal of Women's Health. 7:113–126.2015
M2の藤澤空見子です。
先日、武藤研究室の2015年度オリエンテーションが行われました!
毎年4月半ばに行われるこのイベントは、新しくメンバーに加わった学生やスタッフの皆様へ向けた研究室紹介(利用ルールやメンバー紹介など)を通じ、お互いの親睦を図ることを目的としています。
今年は、特任研究員として須田英子さん、学際情報学府M1として佐藤桃子さんを4月から新たなメンバーとしてお迎えしました。
また、昨年度秋からこちらへ異動された澤柳さんに対しても改めて歓迎の意を示しました。
このオリエンテーション後は、毎年参加者総勢20名ほど(!)でランチを食べに出かけるのですが、私は今年も「どこに食べに行くのかな」と楽しみにしながら当日を迎えました。笑
今年のランチは医科研敷地内にあるレストラン「チャオベララーマ」でした。
写真は、この時の様子です。
おいしいランチを食べながら皆さんと親睦を深めることができ、とても楽しいオリエンテーションの締めくくりとなりました。
(M2・藤澤空見子)
第60回(2015年4月17日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
神里:
親子関係不存在確認請求事件
最高裁判所第一小法廷
平成26年7月17日判決
藤澤:
羊水検査を受けることについての女性の価値体系
小笹由香・松岡恵
『日本助産学会誌』20(1):37-47.2006
★当事者優先でご案内していたので、ここで告知していませんでしたが、若干席に余裕がありますので、ご案内します。必ず事前申し込みをお願いします(武藤)。
国際ハンチントン協会会長アン・ジョーンズさん 講演会
アンさんは、神経難病であるハンチントン病(HD)患者会の西オーストラリア支部に長くかかわってきた方です。HDを発病したご主人を在宅中心で介護された後、現在、同じくHDを発病された40歳代のお嬢さんお二人のケアをしておられます。また、2005年から、国際的な患者会の連合会である、国際ハンチントン協会(IHA)の会長として、各国のHD患者が置かれた状況を知る立場にあります。
今回の講演会では、アンさんの個人的な経験をひもときながら、オーストラリアの患者会活動、遺伝子診療、神経難病患者の療養生活などについて学ぶことを目的としています。
講演は英語ですが、逐次通訳のご用意があります。
当事者のみなさまをはじめ、HDのケアに関わっておられる方々、オーストラリアの医療や遺伝カウンセリングに関心のある方など、ぜひふるってご参加下さい。
| 日時: | 2015年4月17日(金)16時~18時 (開場 15時30分) |
|---|---|
| 場所: | TKP品川カンファレンスセンター8階 カンファレンスルーム8D 東京都港区高輪3丁目26-33 03-5793-3571 ※JR品川駅高輪口より徒歩2分 |
| 定員: | 40名(要事前申し込み) |
| お申込み先: | 日本ハンチントン病ネットワーク事務局 |
| 主催: | 東京大学医科学研究所公共政策研究分野 |
| 共催: | 日本ハンチントン病ネットワーク |
M2の藤澤空見子です。
4月2日、学際情報学府にて「研究構想発表会」が開催されました。
これはM2の学生が自身の研究構想を発表する行事で、同級生やM1が発表者に対してコメントしたり、意見交換を行ったりします。
武藤研究室からは、M2である李さんと私がそれぞれ発表しました。
13:00-18:00という長丁場だったのですが、同級生やM1の方々からのコメントはためになるものばかりで、有意義なディスカッションができて自分の発表担当時間があっという間だったように感じました。
また、同級生の研究内容を聞くのもとてもおもしろいですね。
皆さんの発表全てわくわくしながら拝聴し、いい刺激になった1日でした。
私も同級生と同じく、修士論文執筆に向けてがんばっていきたいと思います!
(M2・藤澤空見子)
当研究室では、新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻と、大学院学際情報学府文化・人間情報学コースから大学院生を受け入れています。出願希望者の方には、出願前に面談をして頂くようにお願いしています。
【東大医科研大学院進学説明会】
2015年4月18日(土)に開催される、東大医科研大学院進学説明会にて、数分間ですが、研究室紹介をいたします。詳しくは、東大医科研大学院進学説明会のご案内をご覧下さい。
【オープン・ラボ】
進学を検討されている方のための、オープン・ラボを下記の要領で開催致します。来年度は、オープン・ラボの開催は、この1回だけの予定です。ぜひ5月17日(土)に開催される活動報告会にご参加下さい。残念ながらご予定が合わない場合には、
までご連絡下さい。
| 日時: | 2015年4月26日(日)午後2時~6時 |
|---|---|
| 場所: | 当研究室<会場アクセス> |
| 対象者: | 大学院に進学し、当研究室にて研究することを検討されている方 |
| 内容: | 研究室メンバ―が、研究室案内と進学相談に応じます。 |
| お申し込み: | 参加をご希望の方は、お名前、現在の所属、訪問希望時間を添えて、 までご連絡ください。 |
是非お気軽にどうぞ!
2015年4月より、
特任研究員として、須田英子さん
学際情報学府修士課程1年生として佐藤桃子さん
をお迎えしました。
どうぞよろしくお願い申し上げます!
D3の中田はる佳です。
3月24日にメディカルゲノム専攻の学位授与式がありました。
今年度は、趙さんが修士号を、私が博士号を取得しました。晴れて学位を取得することができてとても嬉しく思うとともに、今後、これを十分に活かしていかなければと身が引き締まる思いです。思えば入学してから3年間、あっという間でした。関西の職場と研究室を往復している間に過ぎていったように思います。それでも無事に修了することができたのは、武藤先生をはじめ研究室の皆様のおかげです。
4月からも臨床試験・治験の語りプロジェクトが続くため、嬉しいことに武藤研との関わりは続きます。院生ブログは後輩に引き継ぎますが、今後は臨床試験・治験語りのプロジェクトから引き続き情報発信をしていきたいと思います。
来年度からは新しくなる「院生室より」をお楽しみに!
*写真は、メディカルゲノム専攻の学位授与式の様子。白金台キャンパス1号館講堂で行われました。
(D3・中田はる佳)
第59回(2015年3月20日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
井上:
What Should Be Disclosed to Research Participants?
David Wendler
The American Journal of Bioethics,13:12,3-8.2013
高島(響):
Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy
Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, et al.
N Engl J Med.372(9):803-13.2015
藤澤:
無侵襲的出生前遺伝学的検査の現状と今後
関沢明彦・左合治彦
『日本周産期・新生児医学会雑誌』50(4): 1202-1207.2015
李:
Competent children? Minors' consent to health care treatment and research
Priscilla Alderson
Social Science & Medicine,65(11): 2272-83.2007
M1の藤澤空見子です。
先日、毎年武藤研究室で恒例行事をなっている「遠足」が開催されました。
来年度入学予定の方々も交え、親睦会という意味合いもこめて、毎年行っています。
2014年度の遠足は、三鷹へ行きました。
訪問場所は、
①三鷹天命反転住宅
②JAXA調布航空宇宙センター
の2箇所でした。


どちらも、普段研究生活をしていてはなかなか出会わない新鮮な体験ができ、非常に楽しかったです。
参加者のみなさんの表情も活き活きしていたのが印象的でした。
リフレッシュして気分を新たに、また勉学に励みたいと思います。
(M1・藤澤空見子)
本日、2014年度、第11回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:2015年3月4日(水)9時30分~12時30分
| 発表者: | 趙斌(新領域創成科学研究科 メディカルゲノム専攻 修士2年) |
|---|---|
| タイトル: | 中国における「優生政策」と生命科学政策の相互作用~無侵襲的出生前遺伝学的検査(NIPT)の運用を中心に~ |
概要:
1995年に施行された中国の母嬰保健法が欧米諸国から批判され、政府が国際的な生命倫理の規範の一部も受容してきた歴史を整理するとともに、NIPTに関する中国と日本の実施状況について調査をしてきた。本報告では、(1)中国における優生政策と生命科学政策の歴史、(2)NIPTをめぐる規制と日本に対する影響の検討、(3)山東省威海市婦女児童病院での実施状況とその対応について検討した結果を報告する
| 発表者: | 李怡然(学際情報学府文化・人間情報学コース 修士課程1年) |
|---|---|
| タイトル: | 医学系研究における子どもの権利―出生コホート研究のテリングとアセント― |
概要:
子どもの環境保健への関心の高まりから、胎児期から長期的に追跡する出生コホート研究が世界的に実施されている。親の代諾をもって研究対象者となる子どもの権利の保障をめぐって、成長後にインフォームド・アセント(賛意)を得ることが議論されているが、研究参加の事実を親から子へテリング(告知)するプロセスについては十分検討がなされていない。
修士課程においては、子どもの権利に関する制度的な保障や論点を整理するとともに、インタビュー調査を通し研究に参加する親の視点を考察する予定である。セミナーにおいては先行研究と概要の紹介を中心に、今後の研究構想の報告を行う。
| 発表者: | 藤澤空見子(学際情報学府 文化・人間情報学コース 修士1年) |
|---|---|
| タイトル: | 非侵襲的遺伝学的検査(NIPT)をめぐる、遺伝カウンセリングと一般市民の関係 |
概要:
2013年4月より、非侵襲的遺伝学的検査(NIPT)の臨床研究が開始された。NIPTは、これまでの出生前検査と比較すると、大々的な報道がなされた点や遺伝カウンセリングの利用が義務化されている点など、特徴的な点がいくつか存在する。
果たして、臨床研究を導入した専門家達は、一般市民がどのような形でこの技術を利用することを目的としているのだろうか。また、2003年度から養成課程が開設された遺伝カウンセラーは、遺伝カウンセリングが義務付けられているこの技術において、科学技術と一般市民の間の介在者として機能しているのだろうか。本研究では、非医師である遺伝カウンセラーという存在が、こうした観点からどのような役割を果たしているのか、科学技術社会論的考察を用いて論ずる予定である。具体的な研究手法は、遺伝カウンセラーへの量的調査(意識調査)と質的調査(インタビュー)を計画している。
今回の発表では、先行研究を踏まえた研究の構想(論理的枠組み)と今後の計画を報告する。
第58回(2015年2月20日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
神里:
World hails embryo vote
Ewen callaway
Nature 518:145-146.2015
岩本:
A review of the barriers to sharing in biobanking
Colledge, Flora, Bernice Elger, and Heidi C. Howard
Biopreservation and biobanking 11.6: 339-346.2013
藤澤:
Scientific Millenarianism
Alvin M. Weinberg
Proceedings of the American Philosophical Society, 143(4): 531-539.1999
李:
Child's assent in research: Age threshold or personalisation?
Marcin Waligora, Vilius Dranseika and Jan Piasecki
BMC Medical Ethics, 15(44): 1-7.2014
本シンポジウムは大変盛況のうちに終了いたしました。(2015/2/12追記)
お天気もよく暖かなおでかけ日和の休日だったにも関わらず、なんと140名以上の方々にご参集いただきました!ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
大阪の勉強会とはまた違った雰囲気で、製薬企業や医療機関等いわゆる専門家の方々からもご意見やご感想をいただくことができました。本プロジェクトで構築中のデータベースは、被験者となる患者さんにご活用いただくと同時に、専門家の方々にもご活用いただけることを願っております。
また、中にはインタビューへの協力を申し出てくださった方もいらっしゃり、メンバー一同とても嬉しく思いました。
データベースのウェブサイトが完成した際には、また皆様にお披露目の機会を設けたいと思っております。引き続き、ご関心をお寄せいただければ幸いです。
読売新聞・朝日新聞にシンポジウムのお知らせを掲載していただきました!(2015/2/2追記)
2015/1/22・読売新聞
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=110969
2015/1/31・朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/DA3S11578557.html
つい先日大阪で勉強会を開催したばかりですが、今度は東京(北里大学)でシンポジウムを開催します。
「そもそも、臨床試験・治験ってなに?」「なぜ、体験談を集めようとしているの?」「体験談を集めて、どんな役に立つの?」といった疑問にお答えするようなプログラムになっております。今回は時間も長めにとり、様々な立場の方が登壇します!色々な角度から本プロジェクトの必要性・重要性をお伝えできるのではないかと私自身も期待しているところです。
今回のシンポジウムを通じて、私たちのプロジェクトを少しでも理解していただき、関心をお寄せいただければ幸いです。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
お申込み、お問合せはこちらから。
--------------------------
臨床試験・治験について語り合おう
~体験談の共有に向けて~
| 日時: | 2月11日(水・祝)14:00~17:00 |
|---|---|
| 場所: | 北里大学薬学部1号館1501講義室 東京都港区白金5-9-1 |
| 対象: | 一般の方、臨床試験関係者、医療関係者、教育関係者等 どなたでもご参加いただけます。 |
| 参加費: | 無料 |
プログラム
ごあいさつ:
武藤香織(東京大学医科学研究所)
佐藤(佐久間)りか(認定NPO法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン)
Ⅰ.ミニレクチャー
1.臨床試験・治験の現状 氏原淳(北里大学北里研究所病院)
2.臨床試験・治験参加者の心理 有田悦子(北里大学薬学部)
Ⅱ.臨床試験・治験の語り
経験談を集めることはなぜ大事なのか 吉田幸恵(東京大学医科学研究所)
Ⅲ.ミニシンポジウム
臨床試験・治験の啓発について ~体験談の多様性をどう活かすか~
中島唯善(日本製薬工業協会 医薬品評価委員会)
楊河宏章(徳島大学病院臨床試験管理センター)
山口育子(NPO法人 ささえあい医療人権センターCOML)
| 主催: | 「臨床試験・治験の語り」データベース構築プロジェクト |
|---|---|
| 後援: | 北里研究所病院バイオメディカルリサーチセンター 認定NPO法人 健康と病いの語りディペックス・ジャパン NPO法人 ささえあい医療人権センターCOML |
| お申込み方法: | ・Webサイト http://bit.ly/katarisympo にアクセスして必要事項をご記入ください。 ・FAX 裏面お申込み用紙にご記入の上、03-5791-6231に送信してください。 |
| お問い合わせ先: | 「臨床試験・治験について語り合おうin東京」事務局 (北里大学薬学部医療心理学部門 担当:有田・田辺・鈴木) Email: FAX: 03-5791-6231 |
科学研究費助成事業 基盤研究(B)
「臨床試験参加者の語りデータベース構築と被験者保護の質向上に関する研究」
(主任研究者:東京大学医科学研究所・武藤香織、分担研究者:北里大学薬学部・有田悦子)
第57回(2015年2月6日)
本日は、以下の文献が紹介されました。
中田:
「補助人工心臓:小児用の治験参加を緩和 人命優先で厚労省」
吉田卓矢
毎日新聞 2015年1月27日
小林:
「批判的メディア実践と文化プログラムのデザイン」
水越伸
『人工知能学会誌』26(5):432-439. 2011
李:
National Institutes of Health Advisory committee to the Director Final Report-December, 12, 2014
National Children's Study(NCS) Working Group. 2014
本日、2014年度、第10回目の公共政策セミナーが開かれました。
内容は以下の通りです。
◆日時:2015年2月4日(水)10時00分~12時00分
| 発表者: | 井上悠輔 |
|---|---|
| タイトル: | Paper retractions due to incompliance with human subjects protection requirements: Survey on medical papers published from 1981 to 2011 |
概要:
There are few knowledge concerning retractions of medical papers due to ethical reasons. We investigated paper retractions due to incompliance with human subject protection requirements. Our survey on retraction notices in medical journals from 1981 to 2011 identified 99 papers which were mainly retracted because of this reason. We found that these retractions were mainly explained as resulting from the absence of “ethical review” or “informed consent” per se, without sufficient clarification of the researcher's intention, the scale of hazard to human subjects, and the value of research results. Most of them were continuously cited by other researchers, even after their retraction. Editors should clarify how they weigh the potential benefits against risks involved in each decision on retraction, and also solve the current ambiguous status of residual data included in these retracted papers.